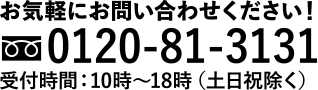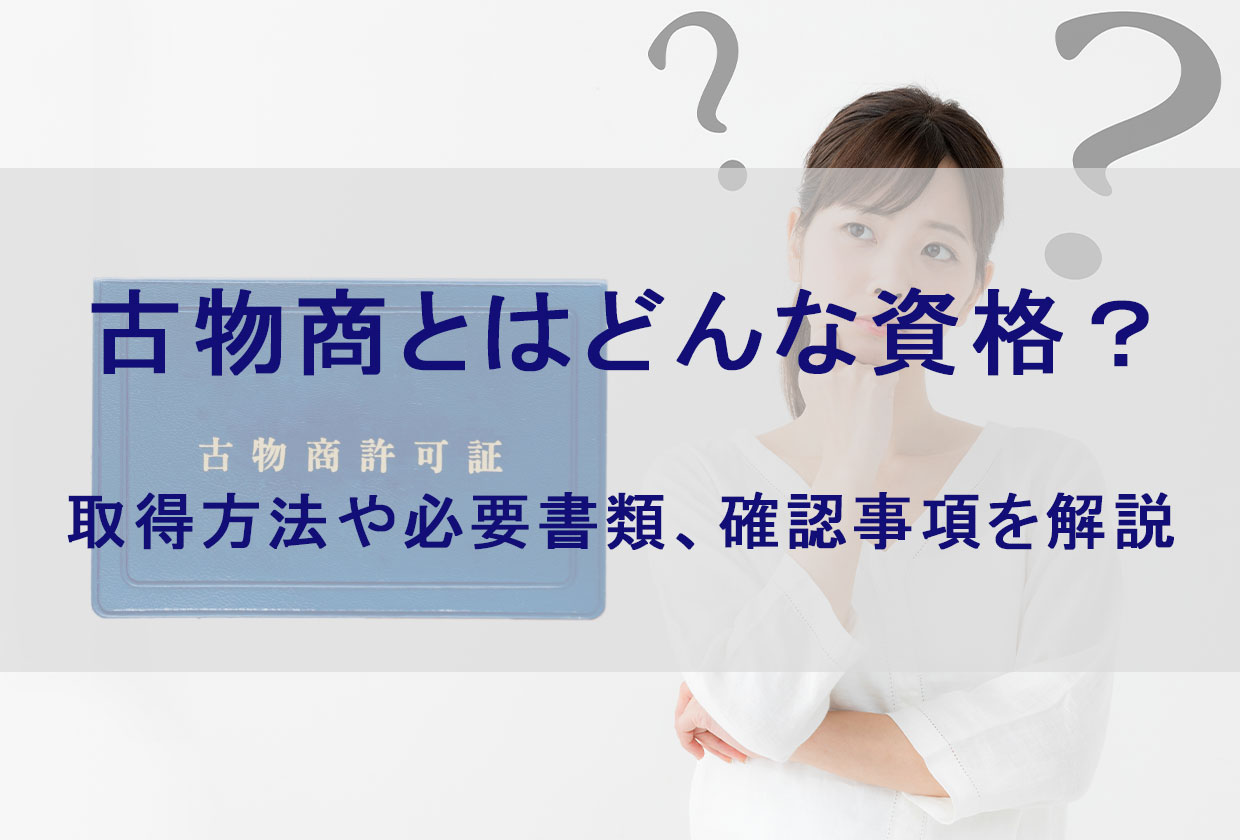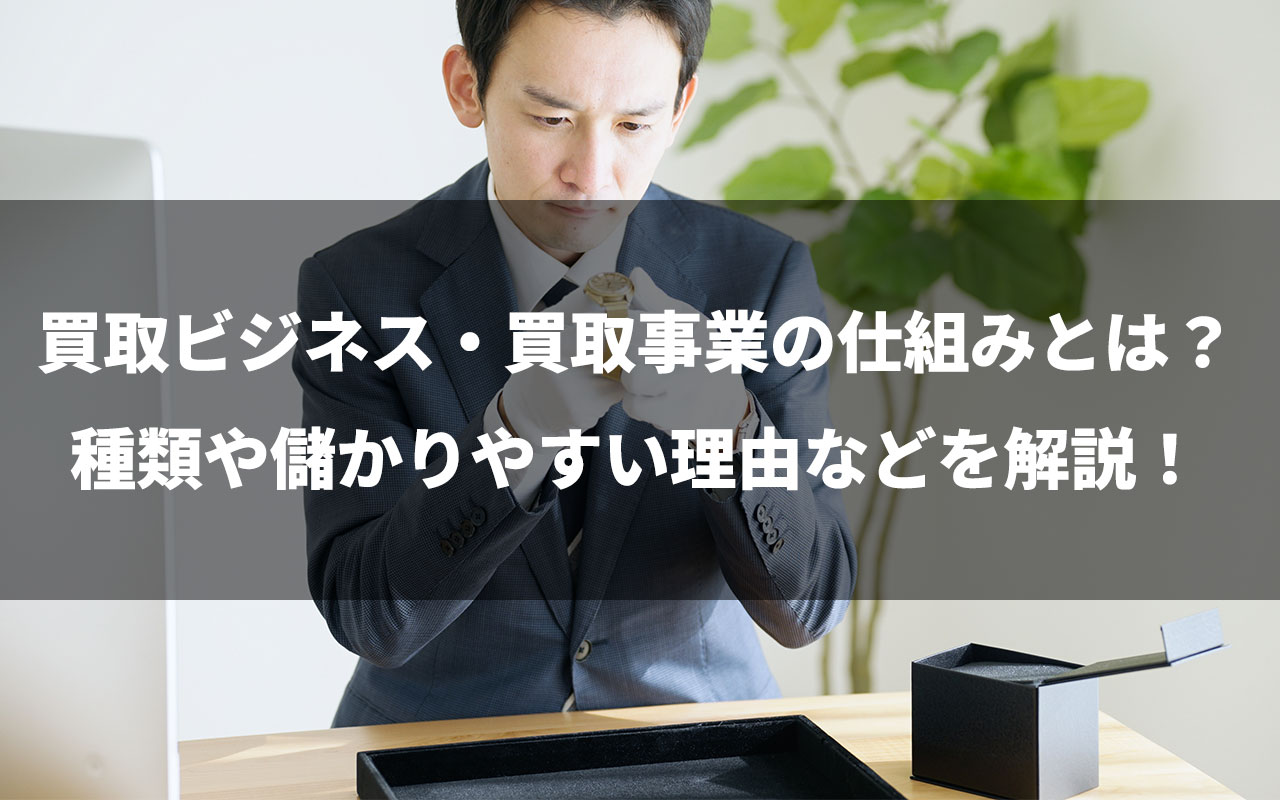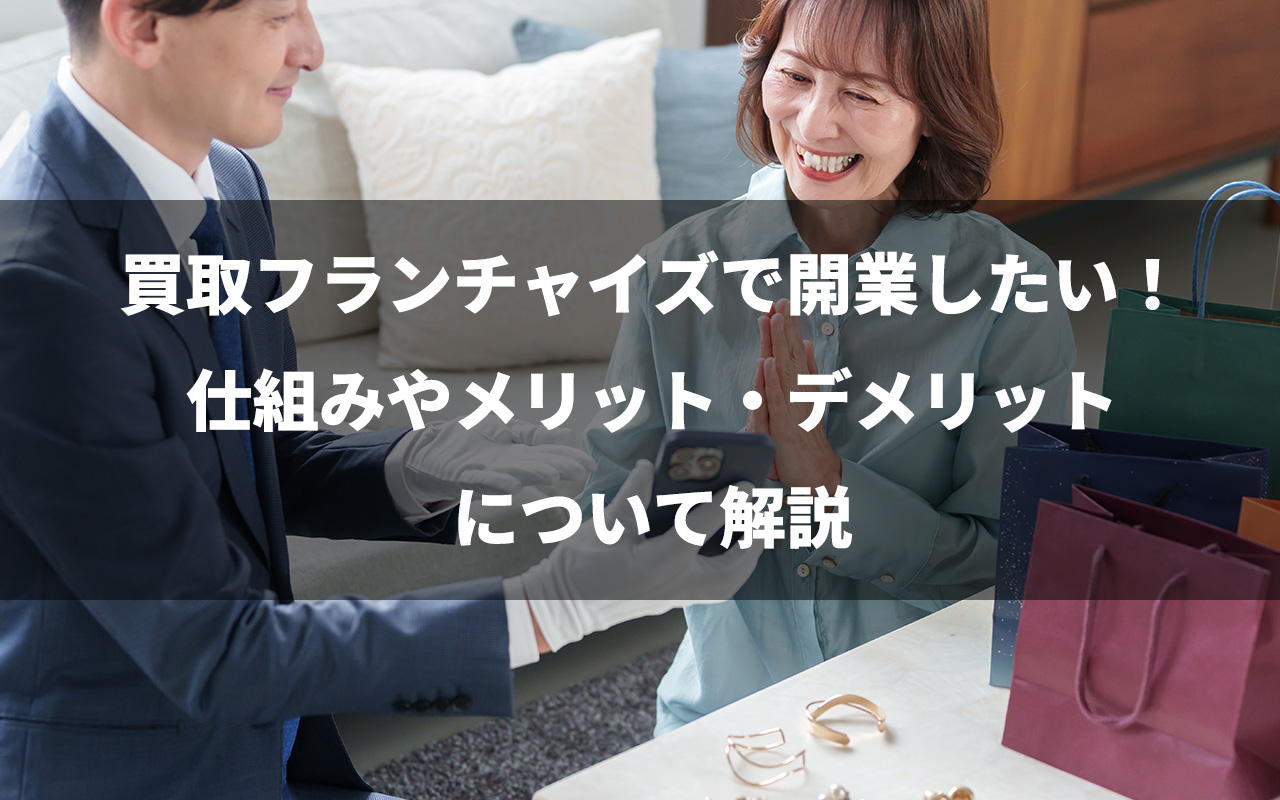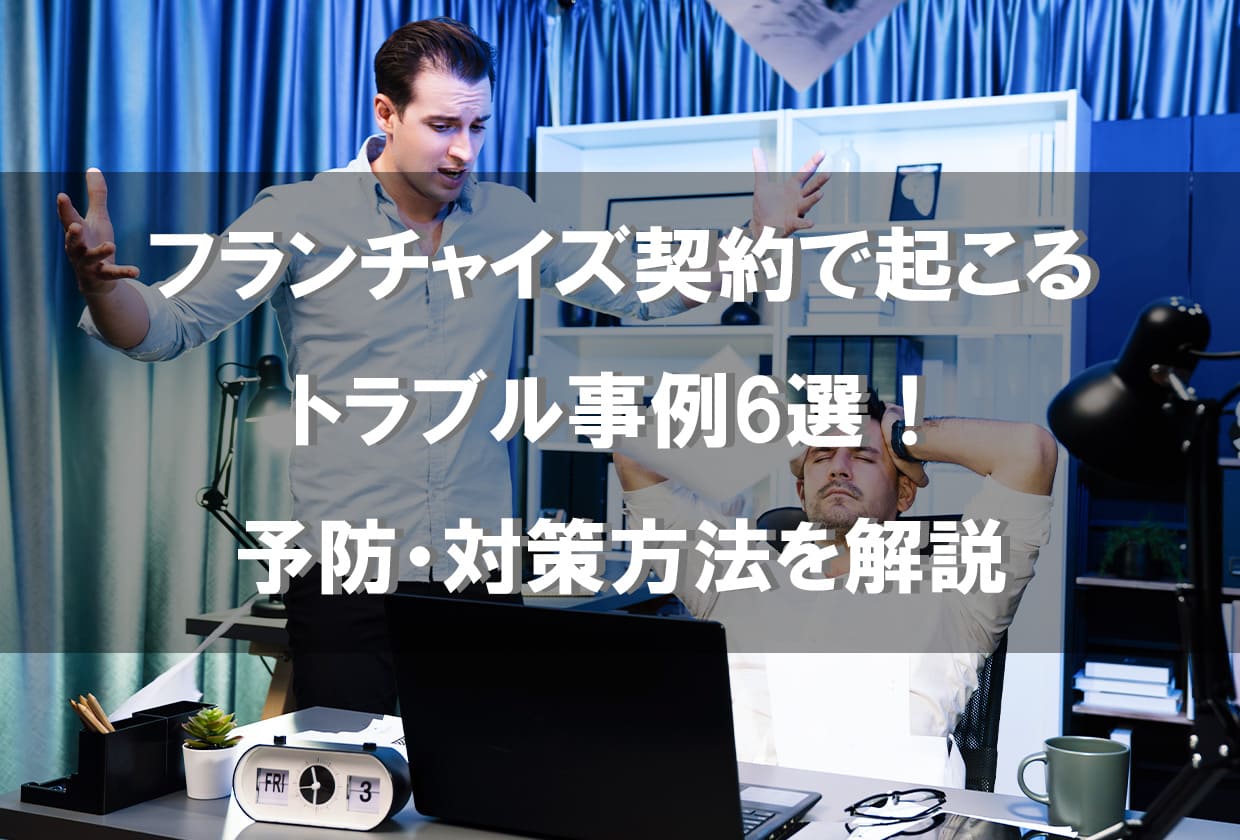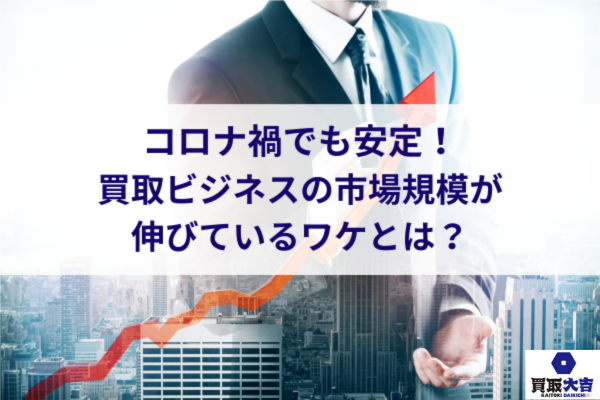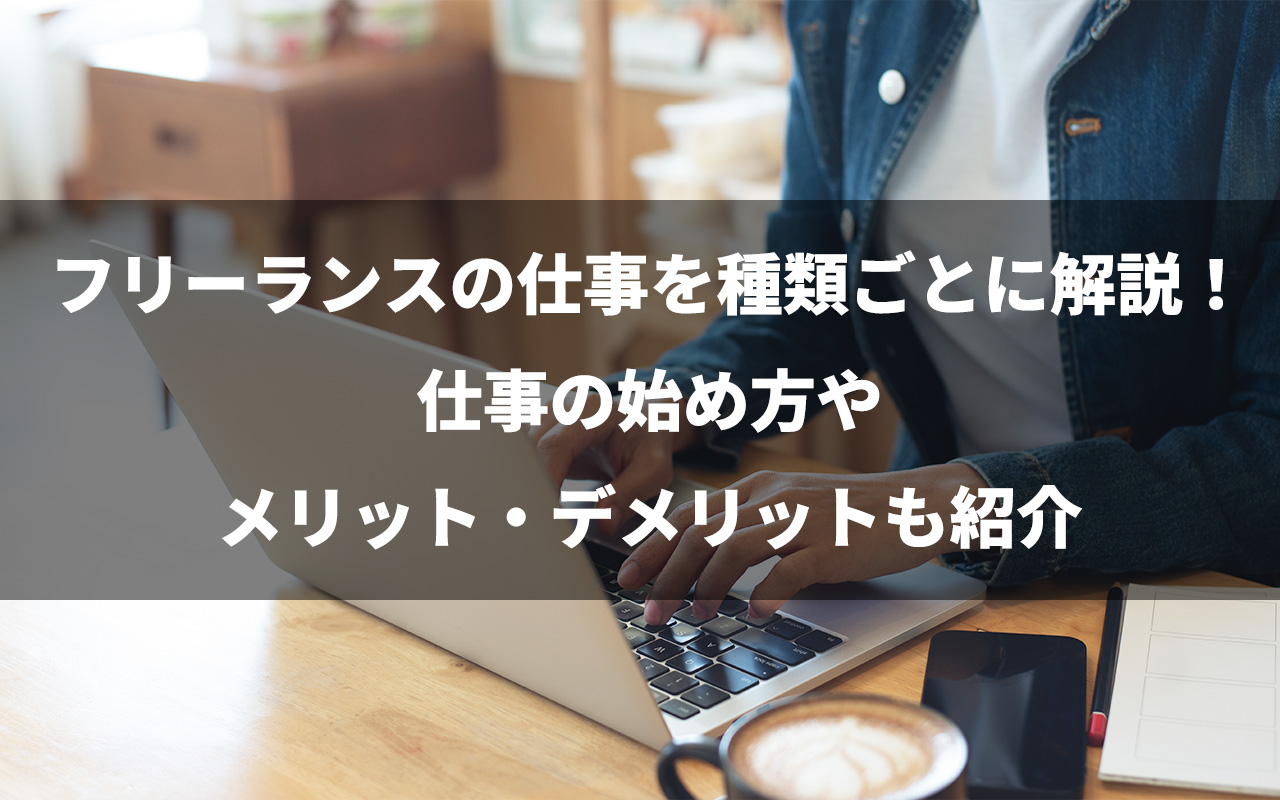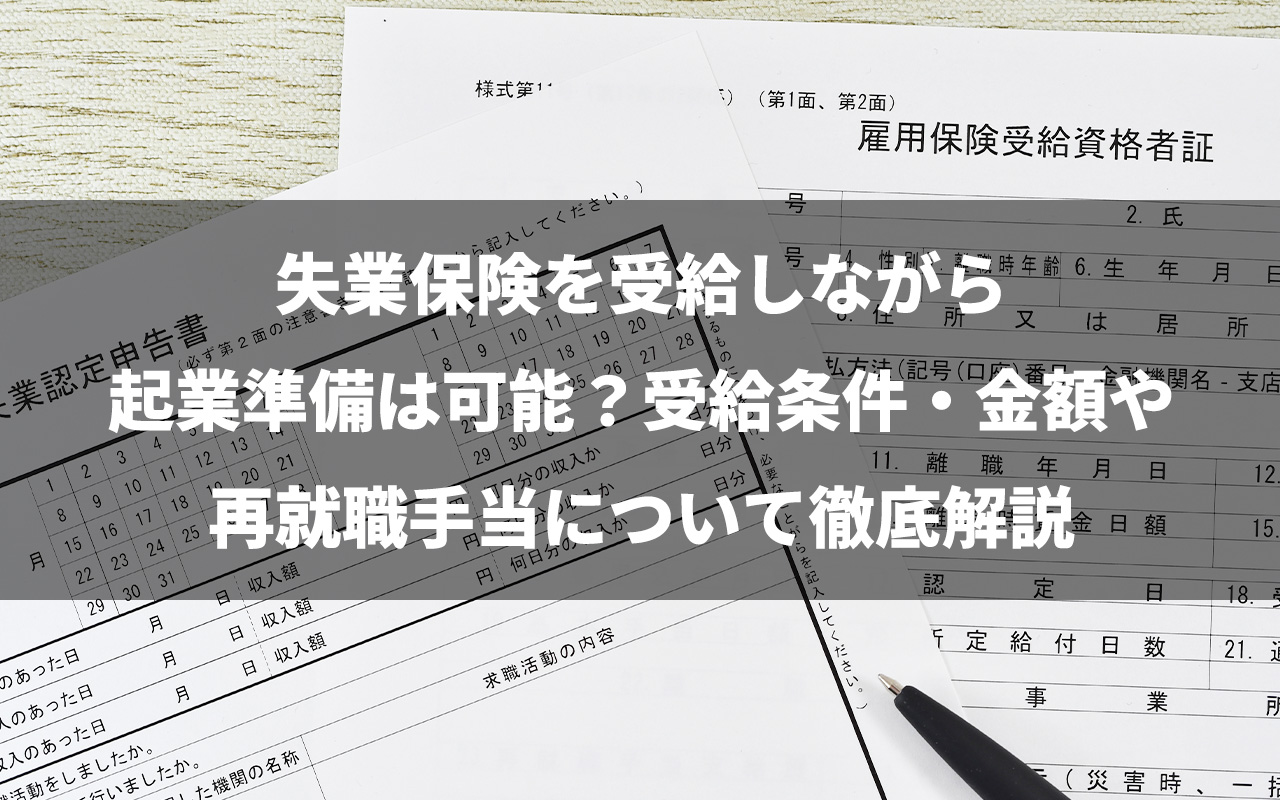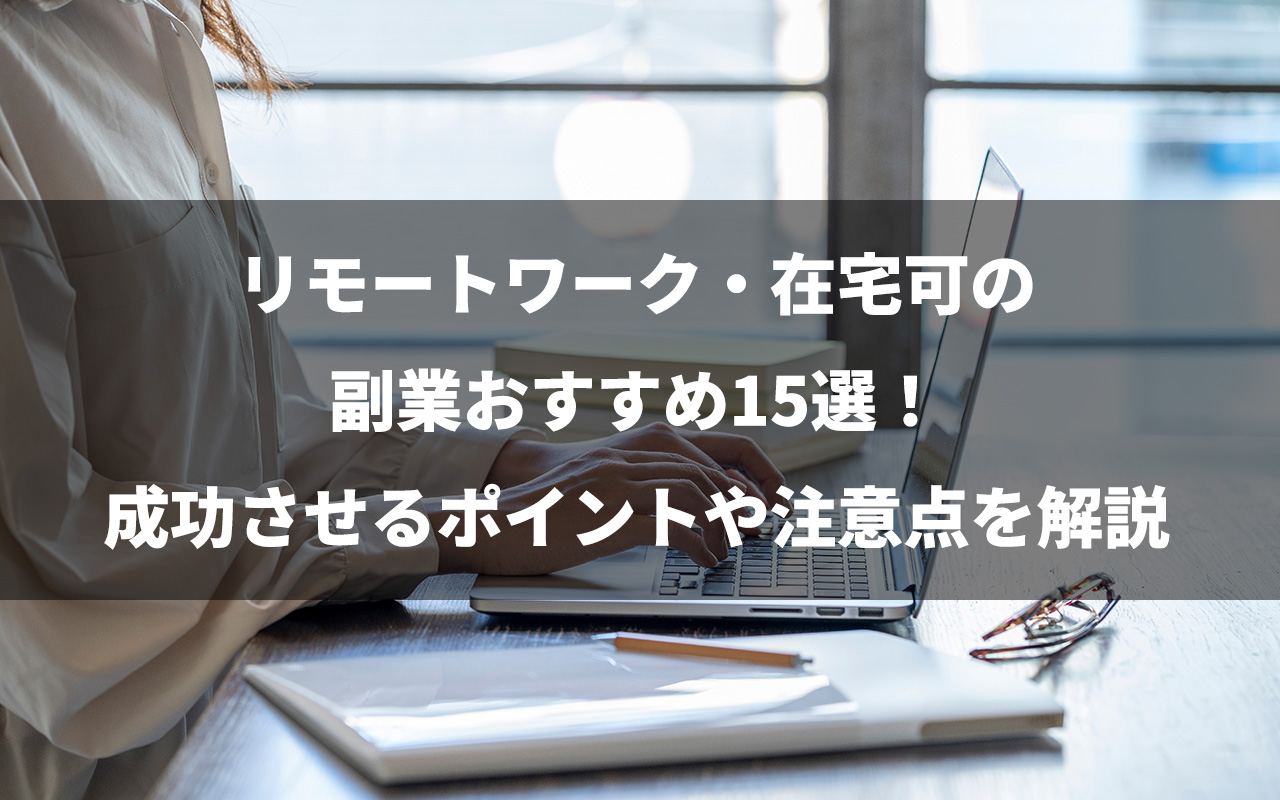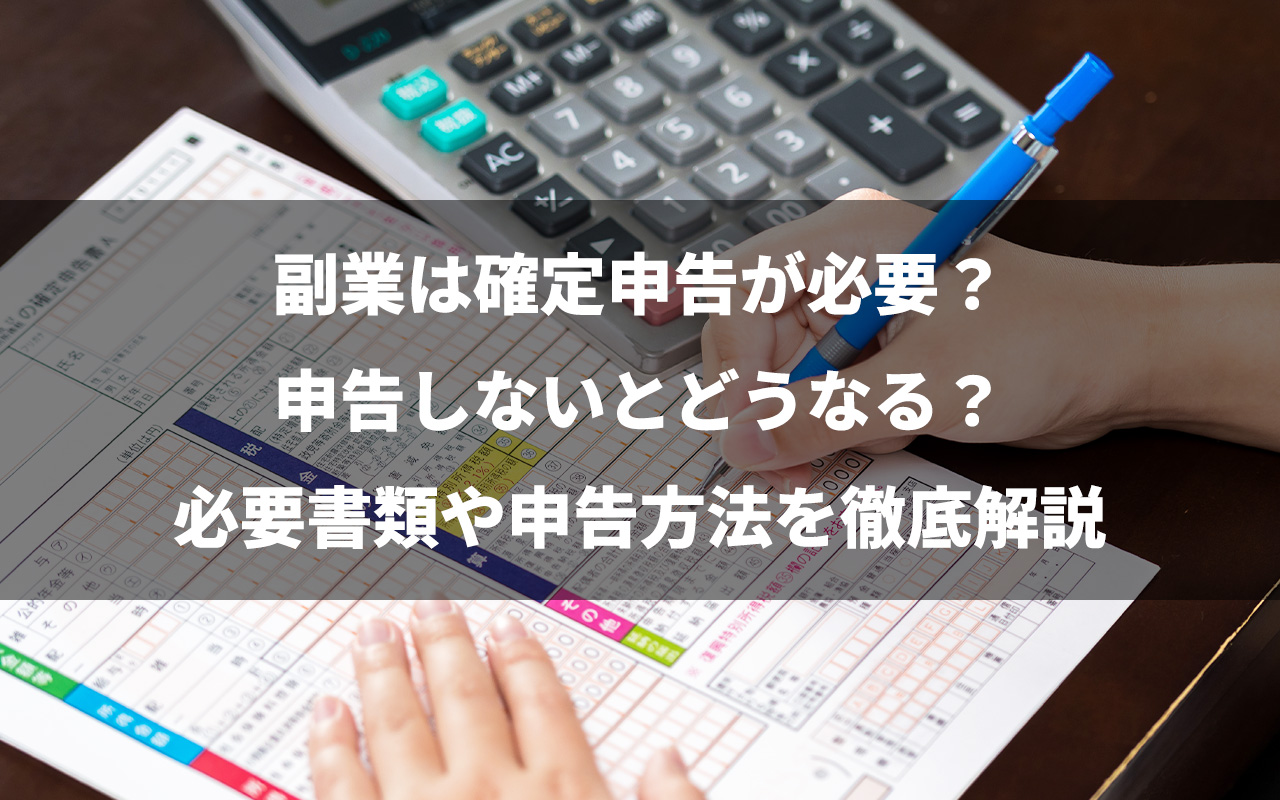古物商とはどんな資格?

古物商とは、中古品を仕入れてそれを売却した時の差額で利益をだすことを指す言葉で、古物商という資格はありません。
ただ古物商を商ううえで、「古物商許可」という資格が必要となることがあるため、古物商=古物商許可のようにいわれています。
古物商の資格を取得する際に事前確認すべき項目

古物商許可の取得には、難しい技能や試験などがないため、手順を踏めば比較的簡単に取得できます。
しかし、事前に確認が必要なことが多いため、ここでそれらについて紹介していきます。
古物商許可が必要な取引
フリマアプリやネットオークションは、今ではだれでも気軽に使えるものになっていますが、古物商の許可を取らず行うと知らぬ間に法令違反になることがあるため注意が必要です。
もちろん、全ての取引がこれに該当するわけではなく、古物商許可がいらない場合もあります。
許可が必要な取引は、中古品を仕入れて売却することで利益を得る場合に適応され、具体的に以下に該当する方は、古物商の許可を取らないと無許可営業になってしまいます。
①中古品を買い取って売る場合
古物商許可が必要な取引の基準にもなっています。
②仕入れた中古品を手直しして売る場合
中古品を手直しして販売したとしても、許可が必要な取引になります。
③仕入れた中古品の使えそうな部品だけ売る場合
意外ですが、中古品を解体して部品やパーツのみを販売したとしても、許可が必要な取引となります。
④商品を預かって、売れたら手数料を貰う場合
これは、委託販売という扱いになり、許可のいる業態になります。
⑤仕入れた中古品をレンタルする
たとえレンタルであっても中古品を扱う場合は許可が必要となります。
⑥中古品を別の品物と交換する
こちらは換金性の高い金などと不正に取引できてしまうため、通常の取引と同様に許可が必要です。
古物商許可が不要な取引
通常では許可証が必要な取引であっても、例外的に古物商許可が必要ない場合があり、それは以下のようなケースになります。
①自分で使用するために購入したものや無償でもらったものを売る場合
自分で使用するために買った中古品のゲームや本、服、他人から無償でもらったものは、例外的に許可証がなくても売ることが可能です。
②海外から仕入れたものを売る場合
中古品の仕入れ先が海外であれば、古物商許可は必要ありません。
ただし、少しでも国内で仕入れの可能性がある場合は必要となるので古物商許可を取得したほうがよいでしょう。
③自分が売った相手から買い戻す場合
相手に古物商許可の取得を強要できない観点から、自分が売ったものを買い戻す場合も許可証は免除されています。
営業所の設定
古物商許可が必要と確認したら、現状で問題なく許可されるかを検討していく必要があります。
古物商許可において、もっとも気をつけなくてはならないのは、古物商として使える営業所の有無です。
古物営業法で言う営業所とは、古物の管理者が常勤し、中古品を仕入れたり、古物台帳(売買の記録)を保管・管理する場所の事をいい、古物商プレート(標識)も掲示する義務があります。
万が一不許可になってしまうと、書類などが無駄になりますし、警察署で申し込み時に払った19,000円の収入印紙代も無駄になるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
勘違いされている方も多いですが、ネット通販を専門とし、顧客が出入りしない業態であっても、古物商許可を取るためには必ず営業所が必要になります。
個人申請では自宅を営業所として申請する方が多く、法人申請では本店所在地にして申請するケースが一般的です。
これらが営業所として使用できるかどうかは、営業所となる物件の所有者が誰なのかによって、許可の判定が変わってきます。
それぞれのケースごとに解説していきます。
自身の持ち物件
許可証を取得する本人が登記上の所有者となっている物件は、その地域で商業行為を禁止されているなどの特殊な場合を除き、営業所として問題なく使うことができます。
営業所の候補のなかでも最も許可されやすい物件ともいえます。
賃貸物件
賃貸物件の場合は、自身の持ち物件の時とは異なり、2つの確認事項をクリアした場合に許可されます。
一つ目の条件は、「物件の借主が古物商許可の申請者であること」です。
賃貸であっても所有物件と同様、古物商許可の申請者と物件の管理者が同一であることが重要となっています。
ふたつ目の条件は「使用目的が賃貸条件を満たしていること」です。
賃貸を借りる際に交わす賃貸借契約書に記述してある使用目的の項目を確認し、古物商の営業所として使える契約になっていれば問題ありません。
しかし、住む為に借りている物件であとから古物商を始めようとした場合、使用目的は住居用となっていると思います。
そのような場合は、古物商の営業所として使用してもよいという許諾を借主から得る必要があります。
具体的な方法としては、古物商営業所としての使用承諾書を作成し、借主さんの捺印をしてもらうことで許可されます。
家族や知人の持ち物件
親族や知人が所有する不動産を使う方法もよく使われている方法です。
このような場合は、古物商の営業所としての使用承諾書を作成し、所有者に捺印してもらう必要があります。
また、物理的実体を有さないバーチャルオフィスは、基本的に古物商の営業所として設定する事はできません。
他に許可の条件はあるか
古物商許可の一番の障害は上述した営業所の確保であり、ここさえ問題なければ基本的には古物商許可は受けられます。
ただし、欠格要件に該当する人には許可がでないため、念のため確認しましょう。
欠格要件に該当するのは、簡単にいうと犯罪を起こした人や、過去に古物商許可を取り消された人が該当します。
刑罰の執行後一定期間経過したり、執行猶予期間が終了していれば問題なく発行されるため、一生申請できないわけではありません。
古物商は個人・法人どちらで申請するか
古物商許可を取得する際に、個人で取る場合と法人で取る場合のどちらで申請するのがよいか考える人がいます。
しかし、個人の古物商許可と法人の古物商許可は全くの別物といえるほど違っているため、この疑問自体が意味のないものとなっています。
はじめて古物商にチャレンジし一つの店舗を運営する場合、個人での申請で十分といえます。
法人で営業する場合、まず株式会社○○リサイクルなどの会社を設立し、株式会社として登記をしなければなりません。
その後、宣伝や商品の売買も全て会社名義で行い、毎年決算期には確定申告する必要がでてきます。
また、一人で個人と法人両方の管理者を兼任することはできませんので、多店舗展開を考えていない場合は、個人免許の方がなにかと都合がいい場合が多いです。
古物商の種類
古物商とは中古品を売買する業態を指すため扱っている内容は多様であり、その種類は13種類にものぼり、以下のようなものが古物商の商品として扱われています。
絵画や骨董品、アンティーク品などを扱う「美術品」。
古着や着物、子供服などを扱う「衣類」。
時計・宝石・アクセサリーなどを扱う「時計・宝飾品 」。
4輪自動車・タイヤ・部品などを扱う「自動車」。
バイク・タイヤ・部品などを扱う「自動二輪・原付」。
自転車・タイヤ・部品などを扱う「自転車」。
カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡などを扱う「写真機」。
パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機などを扱う「事務機器 」。
工作機械・土木機械・電気機械・各種工具などを扱う「機械工具 」。
家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨などを扱う「道具」。
バッグ・靴などを扱う「皮革・ゴム製品 」。
古本などを扱う「書籍」。
商品券・航空券・高速チケットなどを扱う「金券」。
となっており、この中でメインの品目を1種類とそれ以外にも取り扱う予定のあるものを全て選びます。
極端ですが、13種類全てを選択することもできますが、警察署での説明が難しかったり、数台の駐車スペースが必要となるなど品目によっては取得するのに制限があるものもあります。
そのため、実際に取り扱う予定のものや近いうちに取り扱う可能性が高いものだけを選ぶのが一般的です。
管理者の任命
古物商許可を得るためには、営業所に常勤する管理者がいることが必須となります。
ここでいう管理者は、古物売買における責任者のことで、古物台帳を管理している人を指します。
もちろん、申請者自身が管理者になることもできるため、個人で1店舗を運営するために古物商許可を申請する人のほとんどが申請者=管理者となっています。
法人ですと、営業所が複数あるケースも多く、この場合は各営業所に一人ずつ管理者を置かなくてはならないため、この場合は複数人管理者が必要になります。
法人だと営業所が複数あるケースも多いですが、この場合は各営業所に管理者を置かなければなりません。
管理者になるためには条件が3つあり、「営業所に常勤可能であること」「古物商許可を受けた本人もしくはその従業員であること」「欠格要件に該当していないこと」を満たしている必要があります。
ネットで販売する場合のホームページやプロフィールページ
スマートフォンの発展で、インターネットを使った古物の売買は身近なものとなっており、利用者も非常に多くなっています。
じつは、ネットでの古物売買に利用するためのホームページやネットショッピングモールのプロフィールページを使うには、警察署への届出が必要になります。
この届出は、古物商許可の申請時に同時に行え、許可申請の時点でURLの証明を同時に提出するほうが楽です。
URLの証明は、添付資料としてURLの使用権限を疎明する資料を用意するのが一般的で、決まった形式は存在していません。
そのURLと申請者が繋がっているのを示すものであれば認められます。
下にはパターンごとの一例を記していますが、念のため警察署に問い合わせるとよいでしょう。
独自ドメインを取得しているケース
既に自分のサイトや店舗HP用のURLを独自ドメインとして取得している場合は、ドメイン検索サイトでそのドメインの所有者・使用者を確認してみましょう。
確認した際にドメインの所有者または使用者=古物商の申請者となっていれば、それをプリントアウトすれば大丈夫です。
調べた結果、自身の名前が出てこない場合は、ドメイン取得代行会社などに代行してもらっていることが考えられるため、代行会社にそうだんしてみてください。
また、プロバイダからドメイン割当通知書を発行してもらったり、新規にURL使用許諾書を作成する方法もあります。
他社サイト内でページの割当を受けている場合
他社のサイト内にページの割り当てを受けてHPを解説している場合も多いと思います。
この場合であっても、そのURLを使用する権限があるかどうかを証明する必要があり、証明としてよく使用されるのは、プロバイダから送られてきた書類が多いです。
具体例としては、「登録完了のお知らせ」「ドメイン取得証」「ユーザー証明書」「設定通知書」などがあたります。
また、ユーザーのコントロールパネルなどが存在すれば、URLと名前を結びつけるような画面のスクリーンショットを印刷したものでも通用する場合があります。
オークションサイトなどで売買する場合
ヤフーオークションやAmazonなどを利用する場合は、出品者プロフィールなどの固有ページのURLが必要になります。
もしも利用しているオークションサイトやショッピングサイトに、固有のプロフィールページが無ければ、URLの届出自体必要ありません。
URLの届出が必要ないケース
たとえホームページがあったとしてもURLの届出が必要のないケースもあります。
具体的には、インターネットを使った買取や販売をしないことです。
ただし、URLの届出の必要がなかったとしても、取引先とのメールや郵便物・名刺等に許可番号を明記して古物商許可を受けていることを明らかにするほうが望ましいとされています。
書類の提出先
古物商許可は、公安委員会が管轄しており、地域の警察署に書類を提出する必要があります。
詳しい内容については、後述する資格取得の流れを参考にしてください。
古物商の資格取得の流れ

古物商許可は、きちんと手続きを行えば問題なく発行される場合が多いですが、手順や書類がやや複雑なものになっています。ここでは、古物用許可が発行されるまでの流れを紹介します。
1.管轄の警察署へ
古物商許可の申請は、各都道府県の公安委員会(東京都の場合だと警視庁)に対して申請をしますが、実際に書類を提出するのは地域の警察署の生活安全課で行えます。
しかし、どの警察署でもよいわけではなく、営業所のある地域が管轄の警察署でなくてはなりません。
簡単な調べ方としては、まず各都道府県の警察本部を検索エンジンなどで検索し、そこへ電話をかけて古物の営業を行う場所を伝えれば、管轄警察の住所・電話番号などを教えてくれます。
管轄の警察署が確認できたら、その警察署へ古物商許可の申請を行うと電話予約をします。
警察署に出向き。必要な用紙一式がもらえ、申請方法の説明をされます。
今回の手順では、最初に管轄の警察署に行くとなっていますが、じつは申請用紙はインターネットでダウンロードすることも可能です。
しかし、古物商許可を初めて取得する方は、書類作成にあたり管轄警察へ出向くことをお勧めします。
理由としては、古物商許可申請に必要な書類は、申請者の状況によってケースバイケースで変動することが多いからです。
申請料に19,000円の費用がかかるため、ミスをなくすという意味でもこの工程は大切だといえます。
なお、買取店のフランチャイズ契約で古物商許可を取得する場合、企業によってはサポートをしてくれることもあるため、そのあたりはしっかりと契約企業と話し合いましょう。
2.住民票などの必要書類の取り寄せ
古物商許可の申し込み用紙を手に入れたら、必要書類を取り寄せましょう。
ここでは、必要になる書類を紹介します。
①住民票住民票
住んでいる地域の市役所やそのサービスセンターなどで簡単に取得可能です。
記載内容としては、本拠地が記載してあり、マイナンバーは省略したものが必ず必要となります。
金額としては一通につき300円前後で取得できます。
②市区町村発行の身分証明書<1通300円~600円>
身分証明書というと免許証などが思い浮かびますが、これはそのようなものではありません。
自身の本籍地の市区役所で発行される証明書で、一通300円〜600円で発行できます。
本籍地が遠い場合は、郵送などで取り寄せることも可能なため、自分の住んでいる地域によって対応しましょう。
③土地・建物の登記簿謄本<土地600円 建物600円>
古物商の営業所として使用する場所が、自分や親族の名義の物件を使う場合は、土地や建物の登記簿謄本を求められることが多いため、取得しておきましょう。
どちらも600円で取得することができ、取得場所は管轄の法務局になります。
④ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
法人で古物商許可の取得を考えている場合は登記事項証明書も必須となります。
こちらも管轄の法務局で申請しましょう。
3.書類の作成
必要書類の取寄せなどが全て終わりましたら、書類の作成していきます。
以下の書類が記入する必要のあるもので、それぞれ提出するものに差があるため、自分に必要な書類を作成しましょう。
①古物商許可申請書
②5年間の略歴書
③欠格事由に該当しない誓約書
④営業所在地図
これらの4点は申請に必ず必要になるため、しっかりと準備しましょう。
⑤URL使用権限を疎明する資料
インターネットを利用して古物の売買を行うときに必要になる書類です。
自身のサイトを運営する場合はもちろん、ECモールやフリマサイトの場合であっても、自分のストアページのURLが表示された状態で本名が掲載されているページの印刷を求められるケースがあるため、管轄の警察署に確認をしましょう。
⑥賃貸借契約書
営業所が賃貸のときに必要になります。
⑦使用承諾書
営業所が自分名義のものでないときに必要になります。
⑧中古車の保管場所証明資料
中古車を取り扱う場合に必要になります。
⑨その他書類
警察署から別途に必要と指定されたものがある場合、それらも準備しておきましょう。
4.書類の提出・申請
全ての書類が準備できましたら、管轄の警察署へ提出しましょう。
準備するものは、「準備した書類」「運転免許証などの身分証明書」「訂正用の印鑑」「収入証紙代(19,000円)」となります。
申請後、問題がなければ約30日~40日前後に許可の通知がされます。
5.確定申告
これから初めて事業をされる方であれば、税務署に対して開業届を提出する必要があります。
そして、利益が出れば翌年度の確定申告時期に税務署で確定申告をしましょう。
フランチャイズ開業は買取大吉にご相談ください

フランチャイズで買取ビジネスを考えている場合、フランチャイズ本部選びは特に重要な項目です。
買取大吉であれば、開業前の研修や必要書類などのサポートも充実しており、はじめてであっても不安なく開業することができます。
また、店舗を経営していくうえで、不安な点として「適切な査定ができるかどうか」「利益をだし、店舗を続けられるかどうか」の2点がよく挙げられます。
この不安点を解消するために買取大吉ではオンラインによる独自の査定サポートシステムを導入しており、本部に真贋・査定を依頼した商品の売却額を保証しています。
そのため、査定が未経験であっても適切な査定ができ、本部の提示額よりも少ない金額で買い取る事ができればその時点で利益が確定させられます。
そのうえ、開業初日から本部のスーパーバイザーが訪問し、店舗で実践的な現場研修ができるうえ、運営に関する困りごとがでても、その都度オーナーサポート部に電話で相談する事が可能です。
開業前から開業後まで徹底したサポート体制を整えているため、店舗継続率※96.4%と高い数値を記録しています。
※2023年10月~2024年9月のデータです。
まとめ
今回は古物商の資格ともいえる古物商許可証について解説しました。
古物を扱うビジネスの開業を考えている場合、必ず必要になる資格となるため忘れずに取得するようにしましょう。
フランチャイズでの開業の場合、本部企業が取得のサポートをしてくれる場合も多いため、気になる方は確認し、不備なく申請できるようにしましょう。