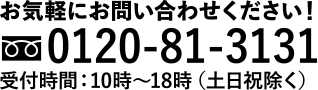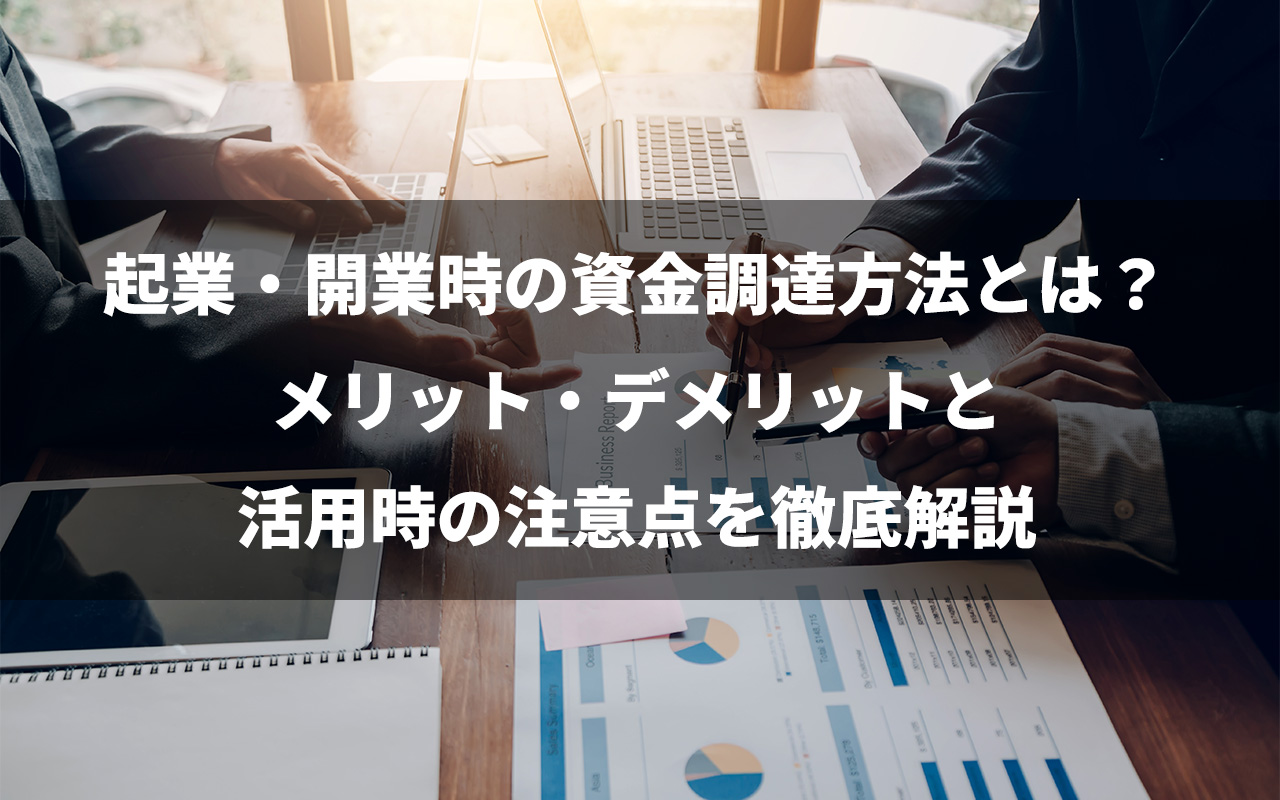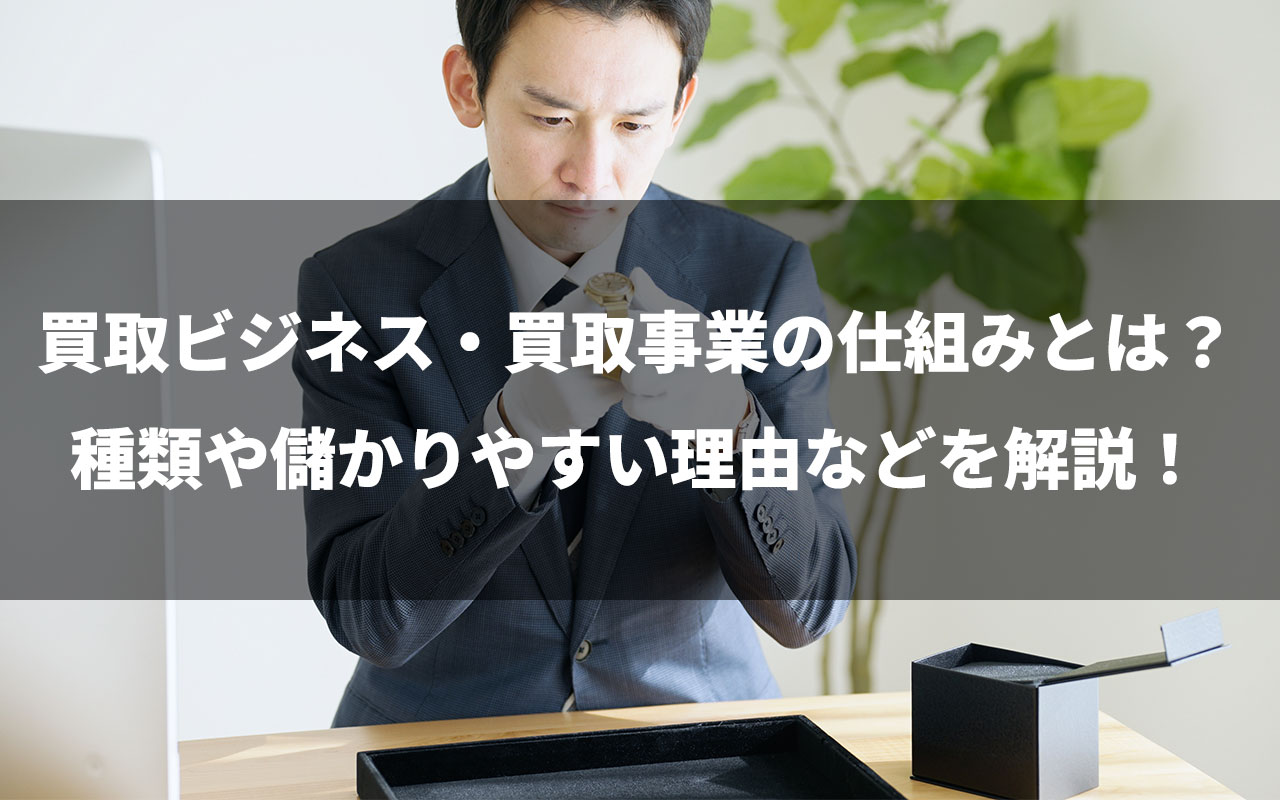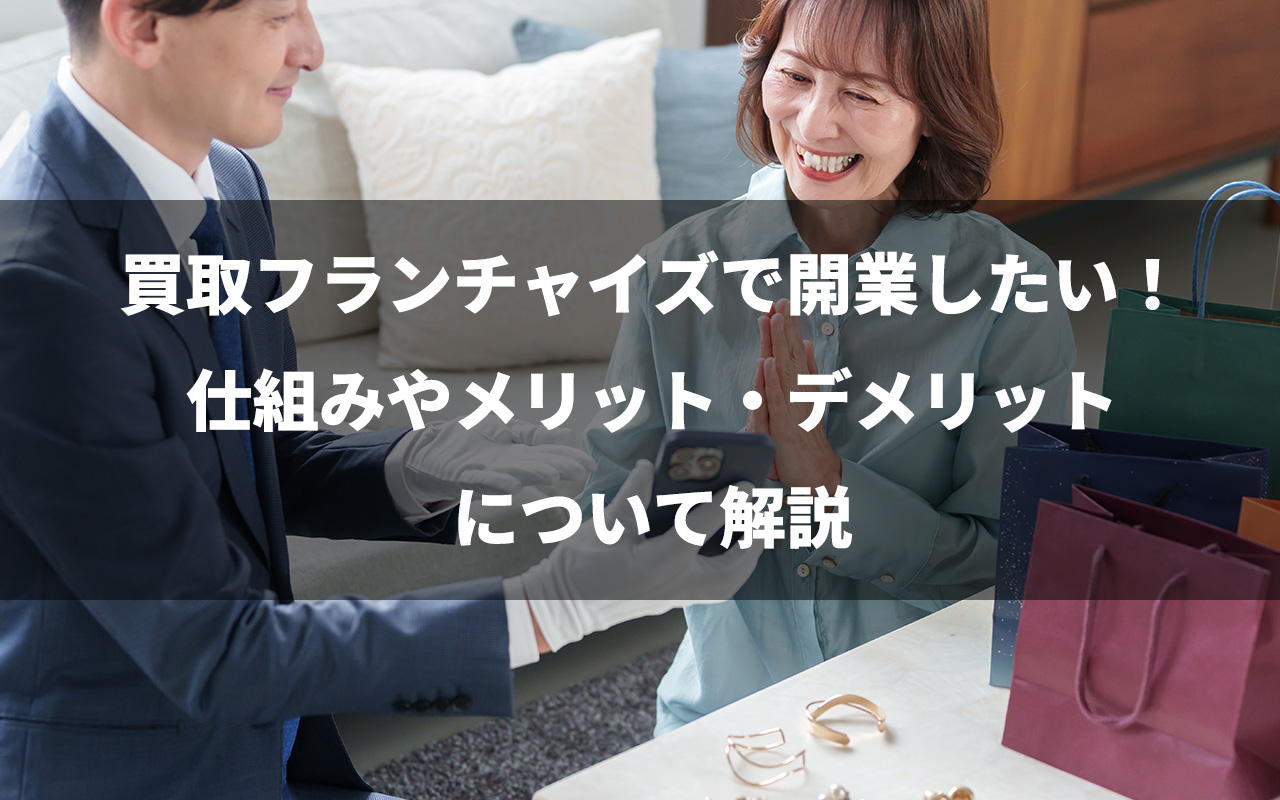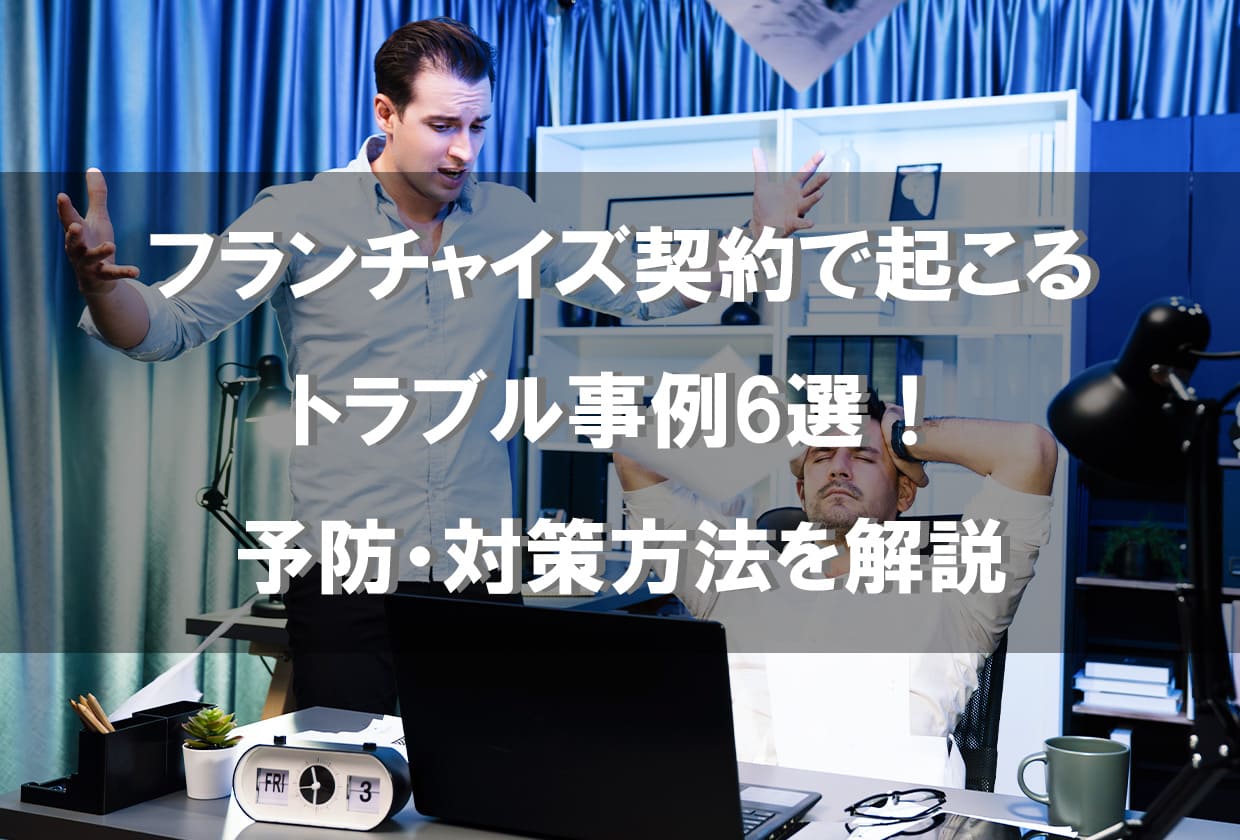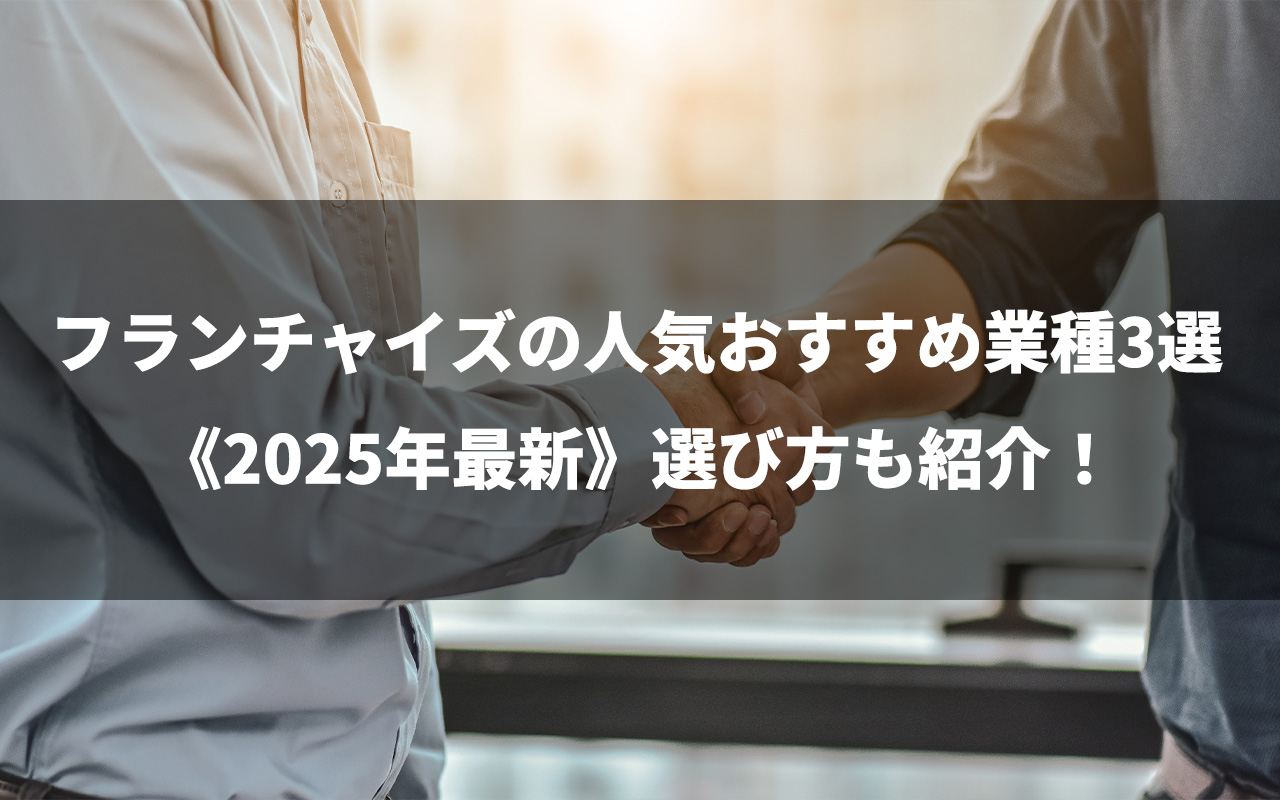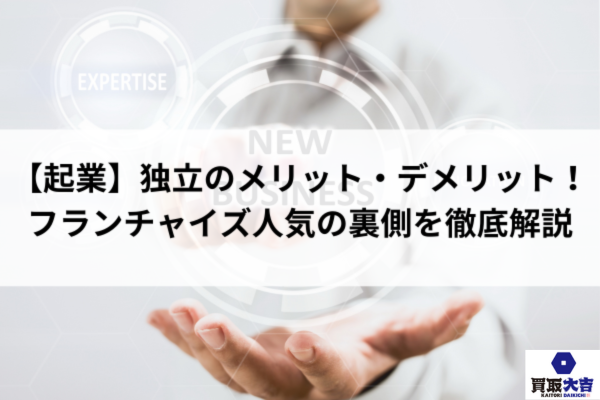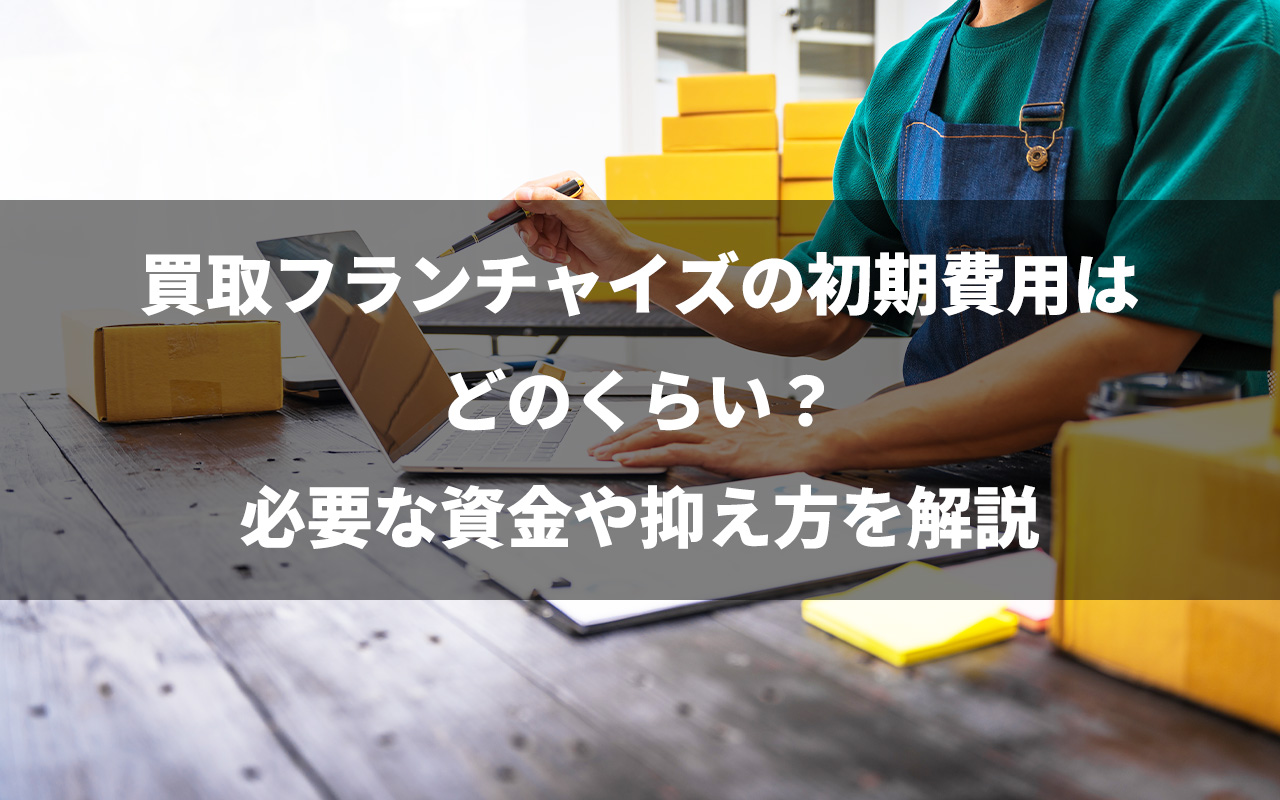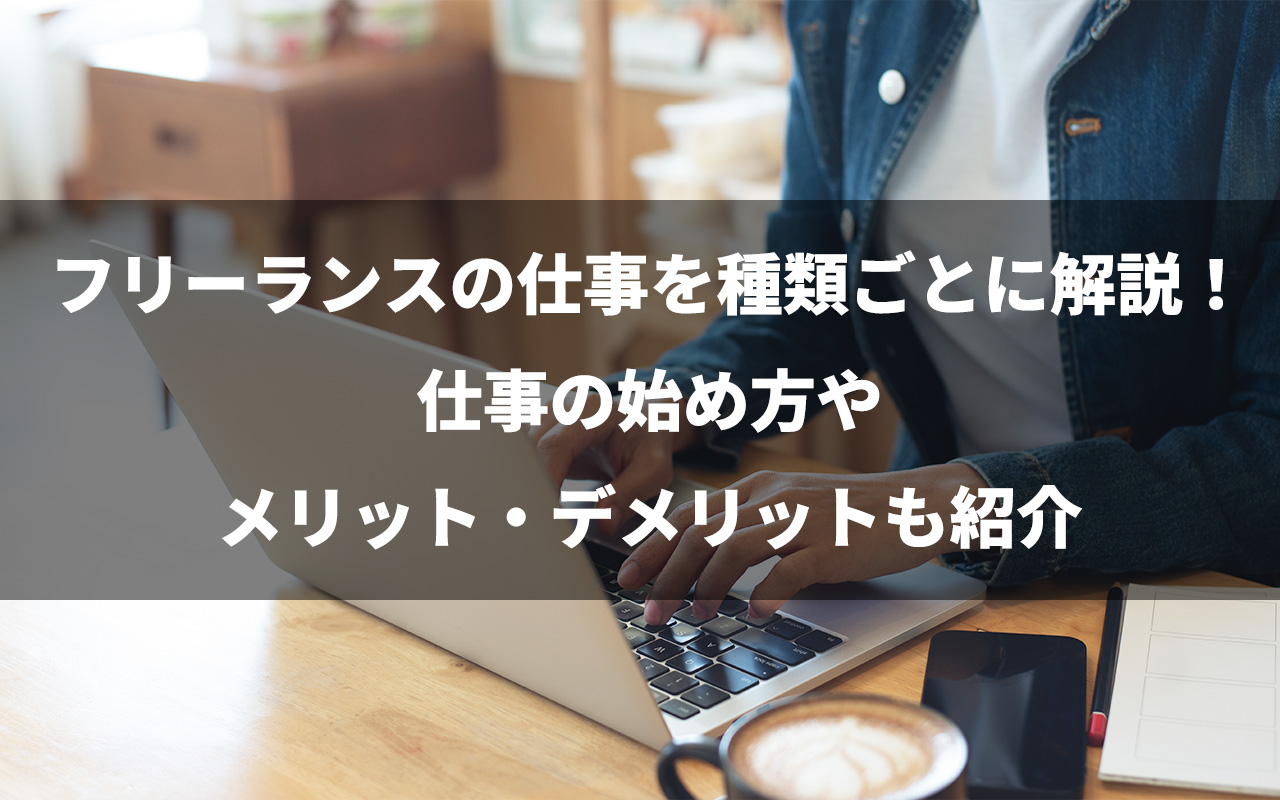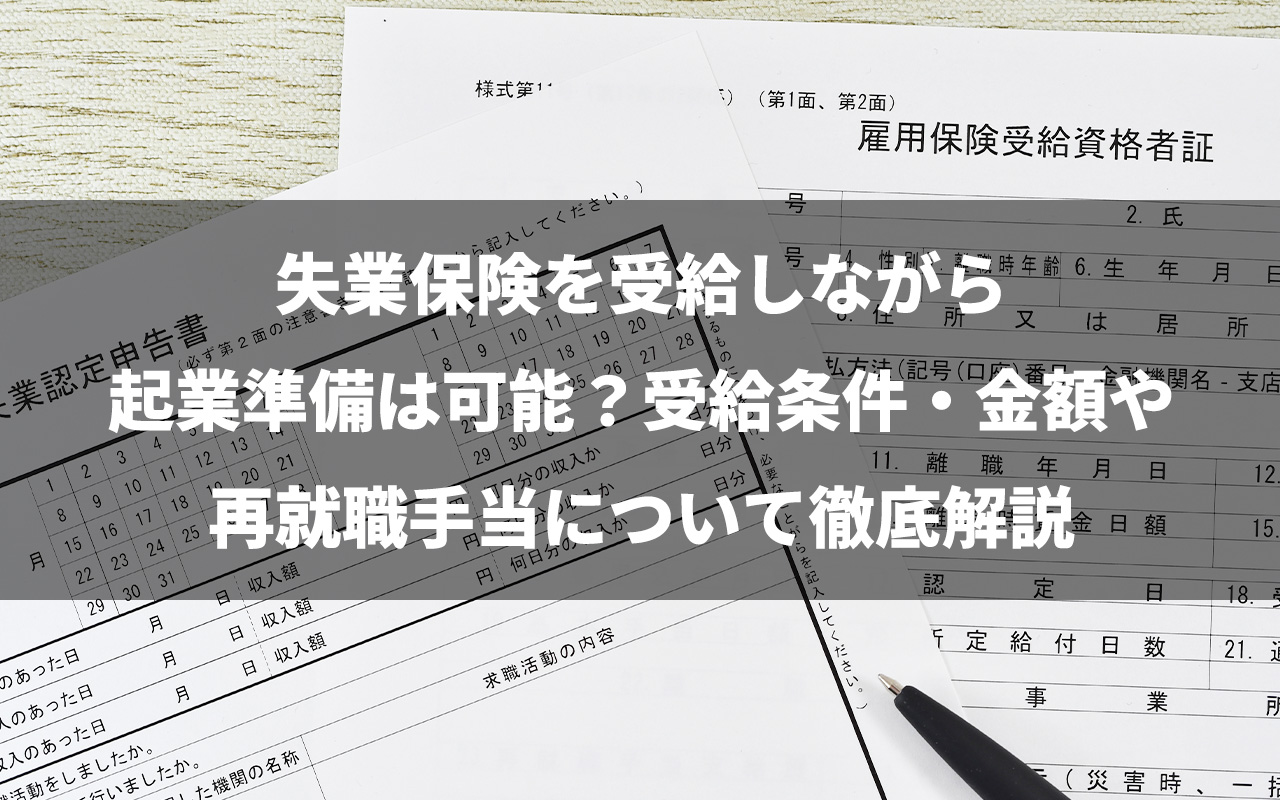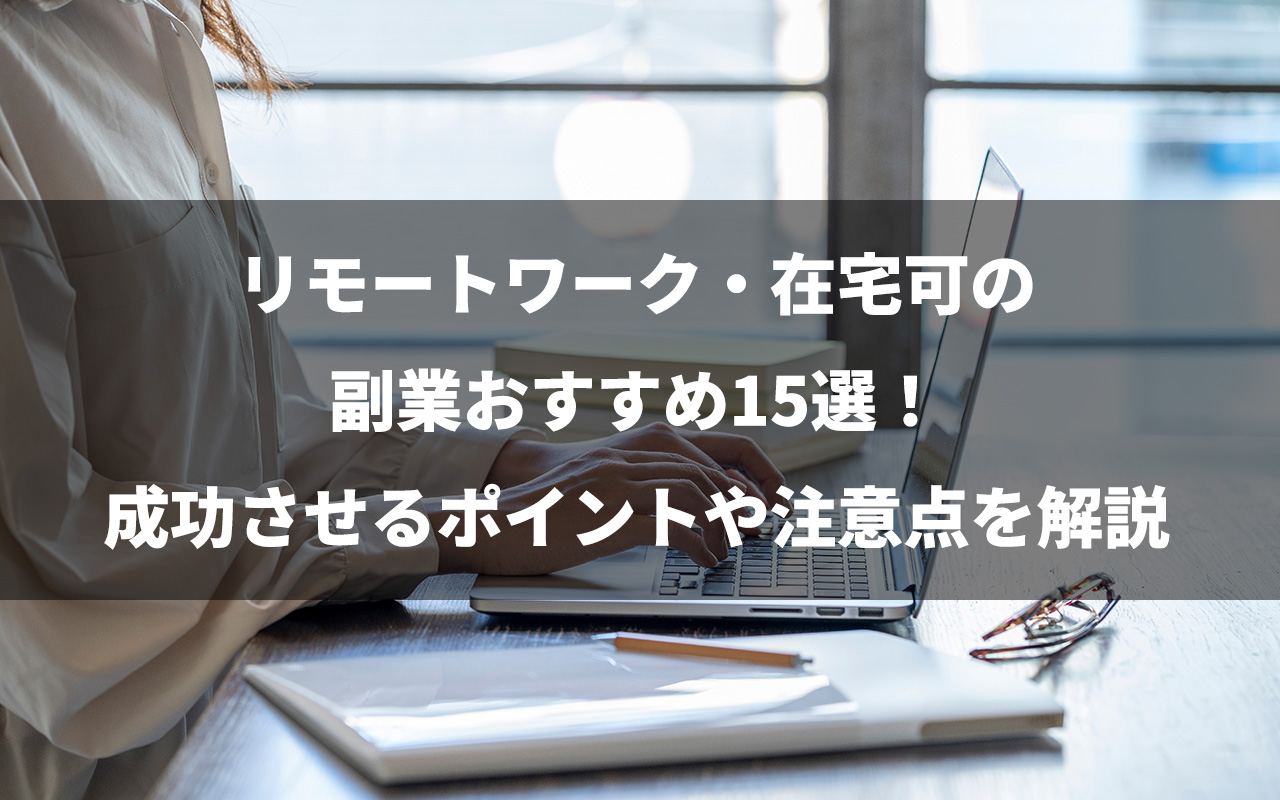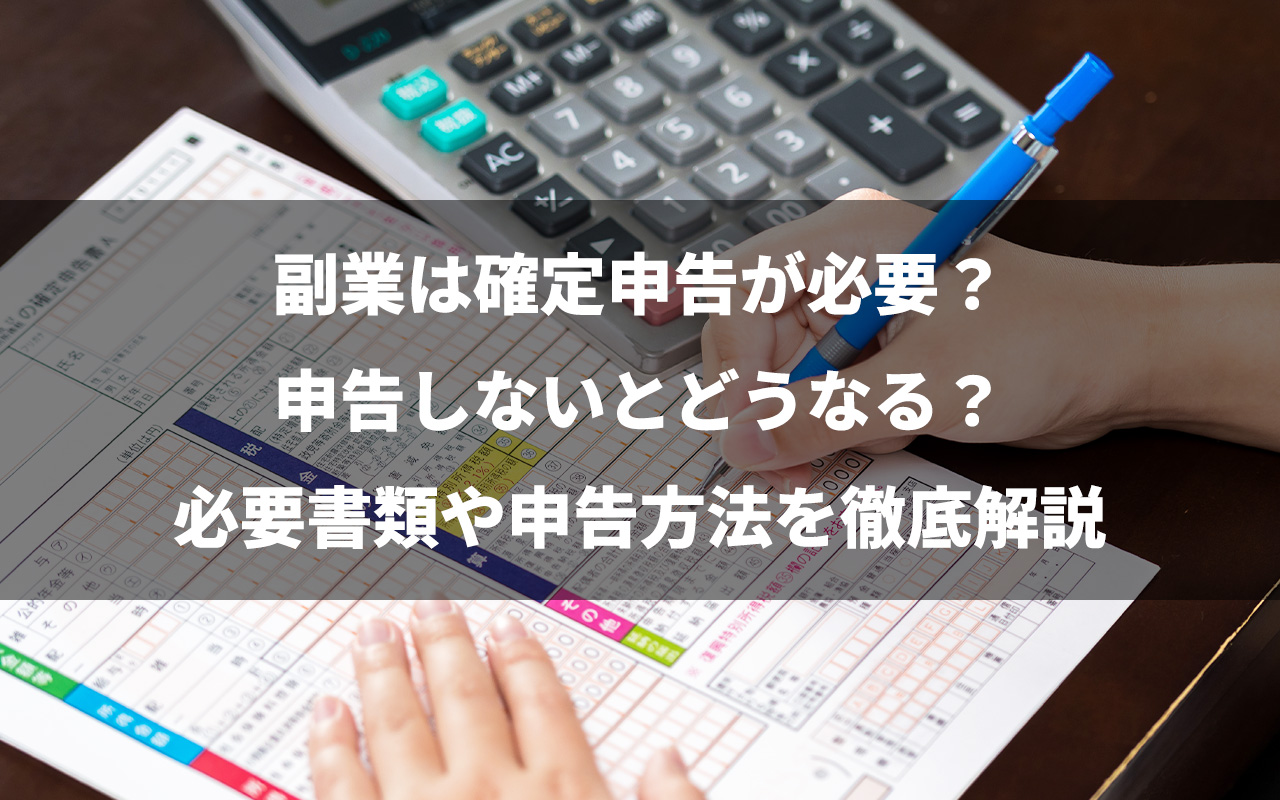事業を行う上で、起業・開業時にも多くの資金が必要となります。
資金調達というと、銀行のような金融機関からの融資を連想する方が多いかもしれません。しかし、資金調達は、融資のほかにもさまざまな方法があり、自社に合った方法を選ぶことが大切です。
そこで今回の記事では、起業・開業、経営のときに役立つ資金調達の方法について解説します。
目次
起業・開業時の主な資金調達方法とは?

起業・開業時に利用できる資金調達方法には、融資以外にも出資や補助金・助成金、資産の現金化などがあります。
この中でどの資金調達方法が適しているかは、事業内容や規模によって異なります。
一例として、これから起業する個人や実績の少ない個人事業主であっても、制度融資や信用金庫であれば、融資を受けやすくおすすめです。
具体的な資金調達方法は後述するため、選ぶ際の参考にしてみてください。
起業・経営の資金調達方法【借入れ・融資】

借入れ・融資による資金調達は、銀行だけでなく制度や公庫など、複数の方法があります。
これらの資金調達方法について、詳しく解説します。
(1)制度融資
制度融資は、地方自治体や金融機関、信用保証協会が連携・提供しています。
審査のハードルが比較的低く、低金利かつ最長10年の長期返済にも対応していることが特徴です。中小企業や個人事業主が利用しやすい制度と言えるでしょう。
また、制度融資では、支払利息や信用保証料(※)の一部を行政機関が補助する場合があります。創業前であっても申込みできるほか、経営相談も対応しているケースもあり、これから事業を立ち上げる方には心強いでしょう。
しかし、複数の機関が関与する関係で融資決定が遅れやすいため、余裕を持って申請するようにしましょう。
※ 融資の返済を信用保証協会が保証するとき、協会へ支払う手数料のことです。
(2)銀行からの融資
銀行が設けた審査を通過すれば、多額の資金を確保できます。
経営への介入がないほか、顧客・ビジネスパートナーの紹介や情報提供が受けられます。さらに、返済スケジュールが明確であるため、資金計画を立てやすいこともメリットです。
しかし、銀行は借り手の信用情報や事業計画の内容を厳しく評価するため、実績が少ない起業直後では、融資を受けることは難しいでしょう。
もしも、起業時に銀行から融資を受けたいのであれば、大手銀行ではなく地方銀行に相談した方が、融資を受けられる可能性が高く、おすすめです。
(3)信用金庫
信用金庫は地域密着型の金融機関で、中小企業を主な対象としてサービスを提供しています。信用金庫の会員から集めた出資金を元手に、企業への融資を行います。
信用金庫のメリットは、実績のない状態でも融資を受けやすいことです。会員を主な対象としていますが、小口融資であれば会員以外の方でも利用できます。また、一般融資以外に制度融資や代理貸付も取扱っています。
ただし、信用金庫は地域の活性化を目的としているため、小口融資以外の取引は、営業範囲内で移住・勤務していなければ利用できません。
(4)公庫融資
公庫融資は、日本政策金融公庫が提供する融資制度のことです。創業支援や中小企業の事業支援などを中心に実施しています。
代表的なメリットとして、銀行などよりも審査を通過しやすいことや、審査結果が出るまでの期間が短いことが挙げられます。また、場合によっては無担保、無保証、低金利で利用できる点も魅力的です。
ただし、事業計画に問題があったり、面談での説明が不十分だったりすると、審査に落ちる可能性があります。さらに、性別や年齢などによって、利用できる制度が限られる点は、デメリットと言えるでしょう。
(5)マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
マル経融資は、小規模事業者の商工業者を対象とした融資制度です。返済期間を10年以内と定めていますが、最大で2,000万円の融資を受けられます。
また、マル経融資は返済できないときに、その損失を補う担保や、代わりに返済する保証人を必要としません。一般的に、融資を受ける際は担保・保証人が不可欠であるため、これらを用意できない方にとっては大きなメリットと言えます。
しかし、この融資を利用するためには、小規模事業者の商工業者が商工会や商工会議所などから経営指導を受けている必要があります。その上で、商工会等の長がその商工業者を推薦していなければなりません。
誰であっても利用できる融資ではない点は、マル経融資のデメリットでしょう。
起業・経営の資金調達方法【出資】

起業・経営の資金調達には、出資を受けるという方法もあります。ここでは、出資による資金調達方法について解説します。
(1)自己資金
個人として保有している資金を、経営者としての自分に出資する方法です。この方法は、起業や経営において、最も基本的であるといわれています。また、金融機関から融資を受けるときの審査などでも、自己資金は重要な要素であるため、十分な用意が必要です。
さらに、この方法では全ての取引が自分のみで完結します。金利やトラブル、経営権等の心配がないことから、自由な経営が可能であると言えるでしょう。
ただし、個人としての資産と会社としての資金の境界を明確にしなければなりません。個人事業主とは違い、法律では個人と法人は別人と認識します。そのため、たとえ自己資金だったとしても、横領罪等に当てはまる可能性があるため、注意しましょう。
(2)従業員持株会
従業員持株会とは、企業の従業員が自社の株式を購入・保有する仕組みのことです。
多くの場合、企業が従業員の福利厚生の1つとして導入しますが、企業側にとっても、安定した資金調達の手段として活用できる利点があります。
しかし、業績悪化で株式が下落したり、配当できなくなったりすると、従業員のモチベーション低下につながるおそれがあるため、導入の際には注意が必要です。
(3)他企業からの出資受入れ
資金を調達するために、外部の企業から出資を受ける方法です。その対価として、資金相当の自社株式を譲渡します。
この場合、株主と株式会社の関係になるため、出資金を返済する義務がありません。ただし、自己株式の保有率が全体の50%を下回ると、出資元の企業が経営権を握ってしまうおそれがあります。
そのため、出資元の企業とは、譲渡比率について交渉し、慎重に判断する必要があります。
(4)ベンチャーキャピタル(VC)
成長が期待できる、未上場のベンチャー・スタートアップ企業へ投資する会社や団体をベンチャーキャピタルと言います。
ベンチャーキャピタルからの出資は、事業の将来性によっては多額の資金を調達できます。また、出資を受けることで社会的信用が高まるため、ほかの手段での資金調達がしやすくなるでしょう。
さらに、ベンチャーキャピタルによる成長支援を通して、経営ノウハウを学べます。
しかし、ベンチャーキャピタルは、出資先の企業に迅速な成長を求めるため、経営へ介入することがあります。出資を受ける際は、株式の一部を譲渡するため、経営へ影響を与える可能性も考慮しなければなりません。
(5)エンジェル投資家
エンジェル投資家とは、将来性のある企業へ資金を提供する、個人の投資家のことです。
出資額は数百万円から数千万円規模と幅広く、起業前後により実績が少ない状態であっても、資金を調達できる可能性があります。
さらに、エンジェル投資家は経営者として成功した方も多く、投資の際に優秀な人材や取引先などを紹介されるかもしれません。
ただし、投資家とのビジネス関係は、前述の外部企業から出資を受ける場合と変わりません。
投資家は株式の所得割合によって経営に介入できるため、投資額や株式の取得割合、投資期間といった出資条件について慎重に決めることが重要となります。
(6)クラウドファンディング
クラウドファンディングは、実現したい事業をプロジェクトとして掲げ、WEB上で不特定多数の方から資金を調達する方法です。
クラウドファンディングを活用することで、金融機関からの融資や投資家からの出資を受けにくい起業前後であっても、事業資金を調達できる可能性があります。
さらにクラウドファンディングは、テストマーケティング(※)の手段としても有効です。プロジェクトへの支援状況や支援者からのフィードバックを通じて、商品の改善点や顧客のニーズを把握できるメリットがあります。
しかし、クラウドファンディングは、支援金が集まらないおそれがあります。そのため、確実な資金調達方法とは言えませんが、選択肢の1つとして検討するとよいでしょう。
※ 新商品を限定的に展開する手法のことです。本格的に展開する前に評価を収集することが主な目的となります。
起業・経営の資金調達方法【補助金・助成金などの制度】

補助金・助成金などの制度を活用することで、起業したてでも資金調達が可能です。
具体的にどのような制度があるのか、詳しく解説します。
(1)創業向けの補助金・助成金
創業向けの補助金・助成金を使うことも、資金調達の方法の1つです。これから起業する場合は、以下のような補助金・助成金を利用できます。
・ものづくり補助金
・中小企業新事業進出補助金
・小規模事業者持続化補助金
・事業継承・M&A補助金
・キャリアアップ助成金
いずれも雇用促進や職場改善などの活動を支援します。また、融資と違い、返済は必要ありません。
そのほかにも、各都道府県が設けている創業者向けの補助金・給付金もあります。
そのため、起業しようとしている地域で利用できる制度について、調べてみるとよいでしょう。
(2)再就職手当
再就職手当は、支給の要件を満たした雇用保険の被保険者が、ハローワークで手続することで得られる就業促進手当の1つです。
また、再就職手当はこれから起業する方も受け取れます。手当を受けるためには、8つの要件を全て満たす必要がありますが、その中の1つに「待機期間の満了後に、就職もしくは事業を開始したこと」と定めています。
起業は事業を開始したことに当てはまるため、ほかの要件も満たしていれば、手当を受け取ることができます。
ただし、離職理由によっては、給付の条件が制限されることもあります。
例えば自己都合の退職である場合、7日間の待期期間が満了してから1か月間は、ハローワークや転職エージェント等の職業紹介事業者の紹介で就職しなければなりません。
この期間で知人の紹介や広告から就職する場合、再就職手当の対象にならない点に注意しましょう。
出典:「再就職手当についてのリーフレット」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001129215.pdf)(参照:2025-3-28)
起業・経営の資金調達方法【資産の現金化】

資産の現金化は、経営維持や事業の転換に有効な資金調達方法です。ただし、今回ご紹介する方法は既に起業しており、事業を展開している方に向けた方法となります。通常、起業前後の活用は不可能である点に注意しましょう。
(1)資産の売却
企業が保有する不要な資産を売却し、現金化する方法です。土地や建物などの市場価値が高い資産であるほど、多額の現金に変えられます。
また、資産の売却は、財務状況の改善や経営効率の向上にもつながります。例えば、不動産を売却した場合、維持や管理に必要な費用を削減できます。
ただし、買い手次第では買取金額が希望する価格に届かなかったり、売却までに時間がかかったりする可能性があります。
さらに、売却する際は送料や手数料が発生することが一般的であるため、実際に得られる金額は額面どおりではないことも覚えておきましょう。
(2)ファクタリング(売掛債権)
取引の際に生じる売掛債権(※)を外部の企業が買取ることで現金化する方法です。
債権の種類や目的によって利用するサービスは異なりますが、早期に現金化することが目的であれば、買取型ファクタリングを2社間ファクタリングで取引しましょう。
このサービスでは、最短で即日から現金化できる場合があります。また、担保や保証人を必要とせず、返済義務が生じません。資金回収を急ぐ場合は、非常に有用なサービスであると言えるでしょう。
ただし、ファクタリングでは手数料が発生します。企業によって利率はさまざまですが、通常、10~30%程度の高い数値に設定しています。
さらに、2社間ファクタリングを取扱う業者の中には悪徳業者も存在します。安全性を考慮する場合は、知名度のある大手企業を利用しましょう。
※ 製品やサービスを取引する際に発生する、代金を受ける権利のことです。会計上では資産として認識されます。
(3)M&A・事業譲渡
M&Aは、企業や事業の合併・買収の総称です。事業譲渡は、数多くあるM&Aの手法を指します。
一度に多くの資金を得られるほか、獲得した資金をもとに事業拡張を図ったり新事業を立ち上げたりできます。
一方で、買い手が見つかるとは限らない点や、法律によって一定の地域内で譲渡した事業と同じ事業を行えない点がデメリットとして挙げられます。
なお、買い手会社との交渉が複雑化することもあるため、必要に応じて専門家に相談し、計画的に進めるとよいでしょう。
(4)リースバック
リースバックは、企業が保有する不動産をリース会社に売却し、同時に賃貸借契約を結ぶことで利用を続ける不動産取引のことです。
まとまった資金を調達できるほか、売却後も不動産を利用できるため、滞ることなく事業を続けられます。また、固定資産税のような維持費がかからなくなるというメリットもあります。
一方、デメリットとして、不動産の所有権を失うことや、リース料を毎月支払う義務が生じることが挙げられます。リース料の総額は、結果的に売却価格を上回るケースが一般的です。
また、賃貸契約である以上、いつまでも借りられるわけではないこともデメリットと言えるでしょう。
このように、リースバックを利用する際はメリットだけでなく、取引後に直面するデメリットもしっかりと考慮する必要があります。
起業・開業時の資金調達における注意点

起業・開業時の資金調達の中には、重視しなければ失敗につながる注意点があります。
どのような点に注意すべきなのか、詳しく解説します。
事業の信頼性
金融機関や投資家は、事業計画や返済能力などを厳しく審査し、事業の成功を見極めようとします。そのため、資金調達を行う上で、事業の信頼性が非常に重要となります。
信頼性を高めるためには綿密な事業計画を立てることや競合・市場の分析などが求められます。また、客観的なデータに基づき、事業の将来性を説明できると、事業の信頼性が高まるでしょう。
自社に合った方法の選択
自社の状況や事業計画に合った方法を選択することが、資金調達を成功させるための重要なポイントです。
例えば起業・開業する場合、前述した日本政策金融公庫の融資や、補助金・助成金の制度が適していると言えます。一方、既に成長段階に入っている企業は、銀行融資やベンチャーキャピタルが候補となるでしょう。
自社の状況を客観的に分析した上で、最適の方法を選択しましょう。
資金調達額を明確にする
円滑に事業を行うためには、過不足のない資金が必要です。
例えば、過剰な資金調達は、経営を圧迫する要因になる可能性があります。融資の場合は返済の負担が増大し、出資の場合は経営の自由度が低下することが考えられます。
一方で、資金が不足していると、事業計画に従う経営が困難になるでしょう。最悪の場合、事業を継続できず、倒産するおそれがあります。
したがって、資金調達を行う前に、必要な金額を明確にすることが重要となります。
買取専門店での起業は「買取大吉」にお任せください

起業を目指すのであれば、成長を続けている買取ビジネスがおすすめです。
近年では中古品の需要が高まっているため、成功しやすいビジネスとなっています。
「買取大吉」では、フランチャイズ加盟店を募集中です。今回解説した融資や補助金・助成金の申請もサポートしています。
・店舗継続率96.4%(※)を可能にした「店舗OJTサポート」
・直営店の成功事例に基づいた「運営サポート」
・折り込みチラシやWEB広告を活用した「集客サポート」
買取大吉のフランチャイズでは、開業前後の徹底したサポート体制が整っているため、未経験の方でも安心してスタートできます。
※ 2023年10月~2024年9月のデータです。
まとめ
今回は、起業・経営のときに有効な資金調達の方法について解説しました。
資金調達にはさまざまな方法があるため、最適の方法は、事業内容や規模などによって異なります。
また、過剰な調達や不足を防ぐためには、事業計画をしっかりと立て、必要な費用を見積もることが重要です。
今回の記事を参考にした上で、自社に適した方法を選択しましょう。