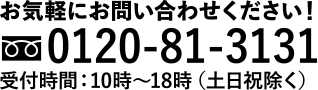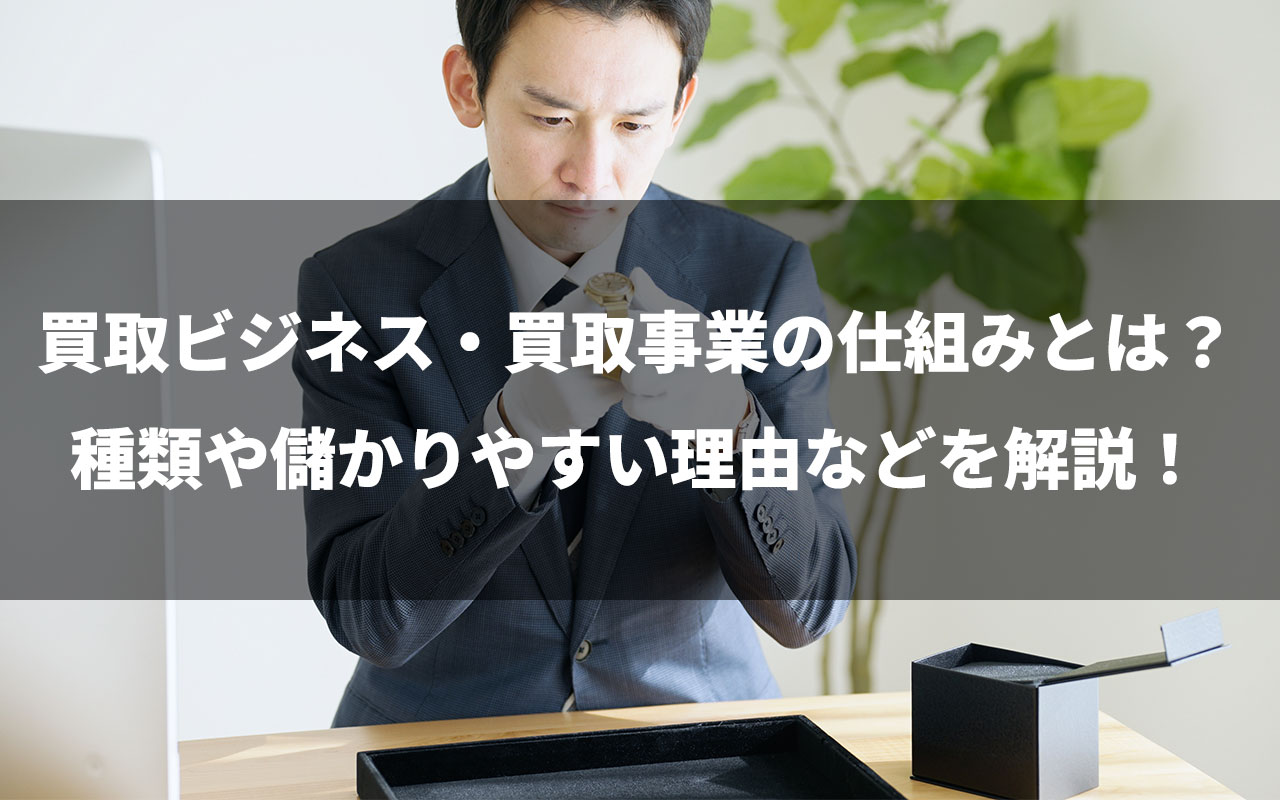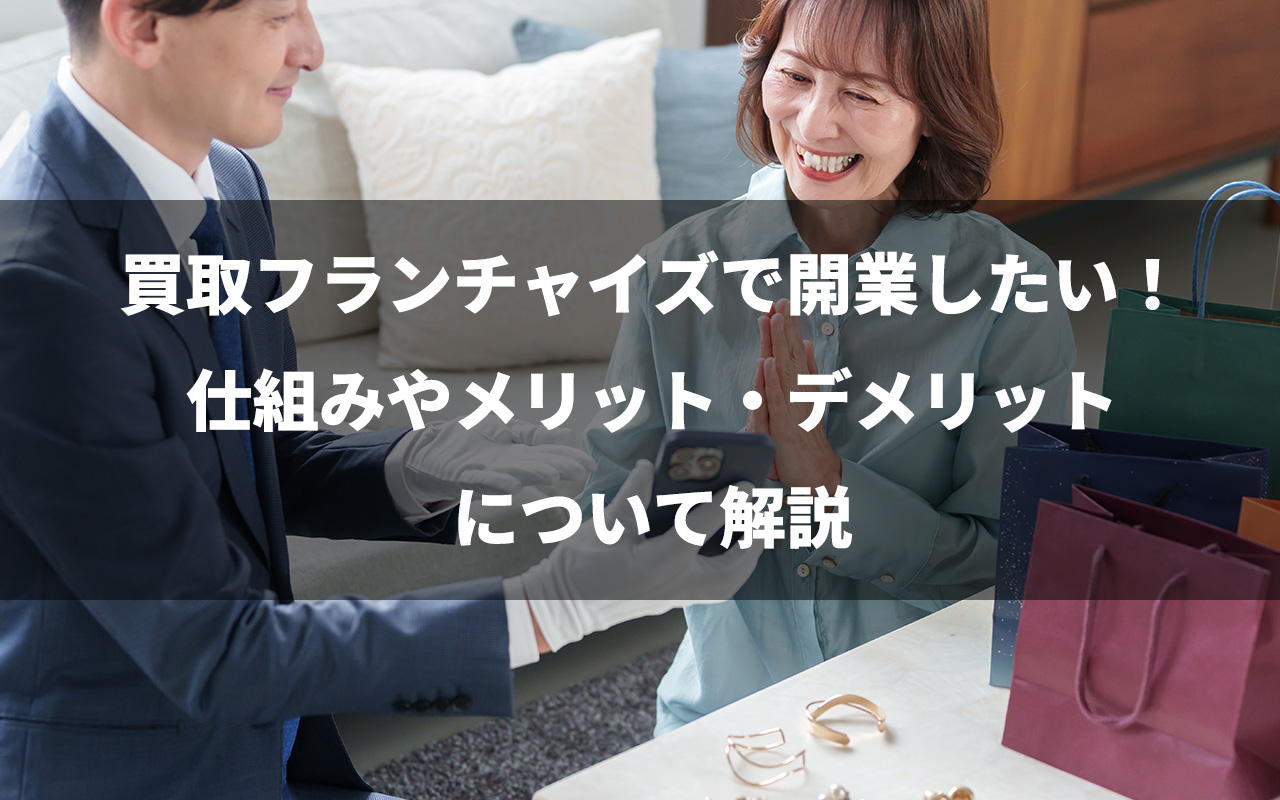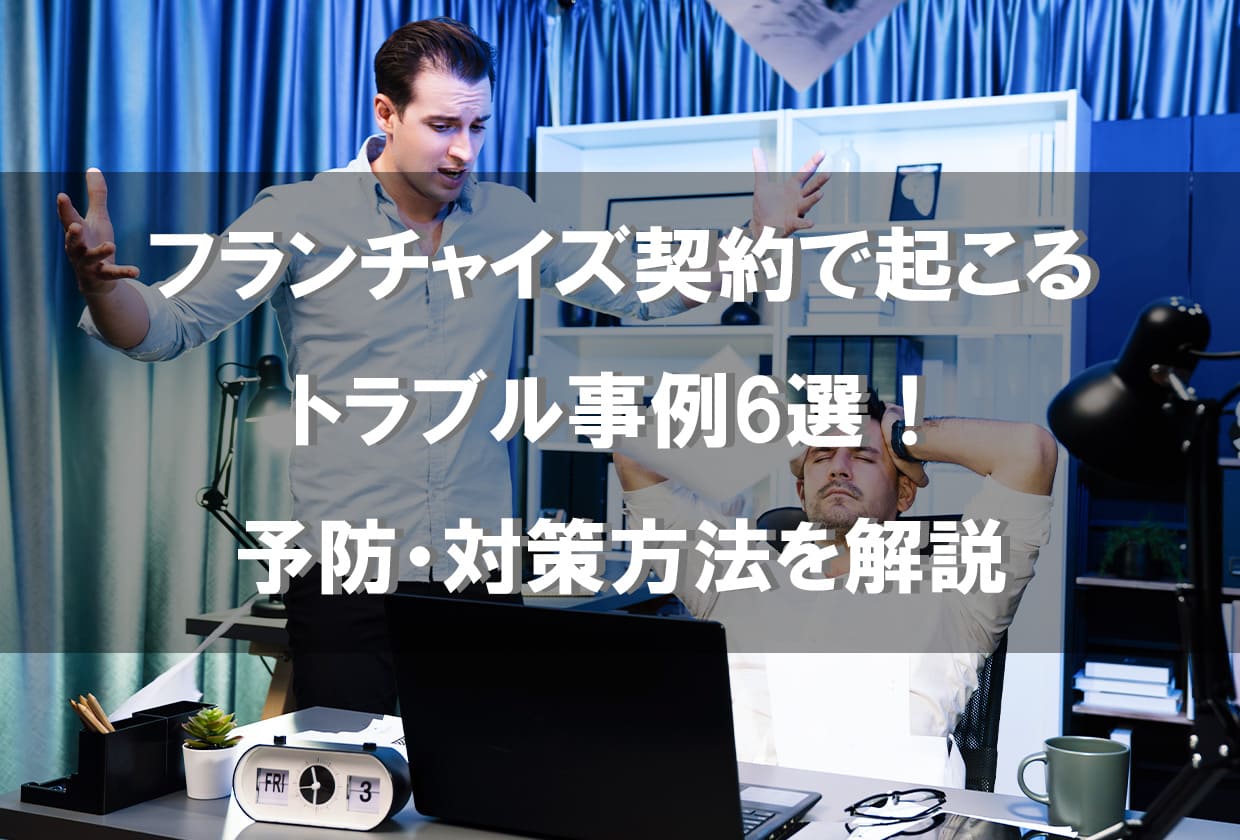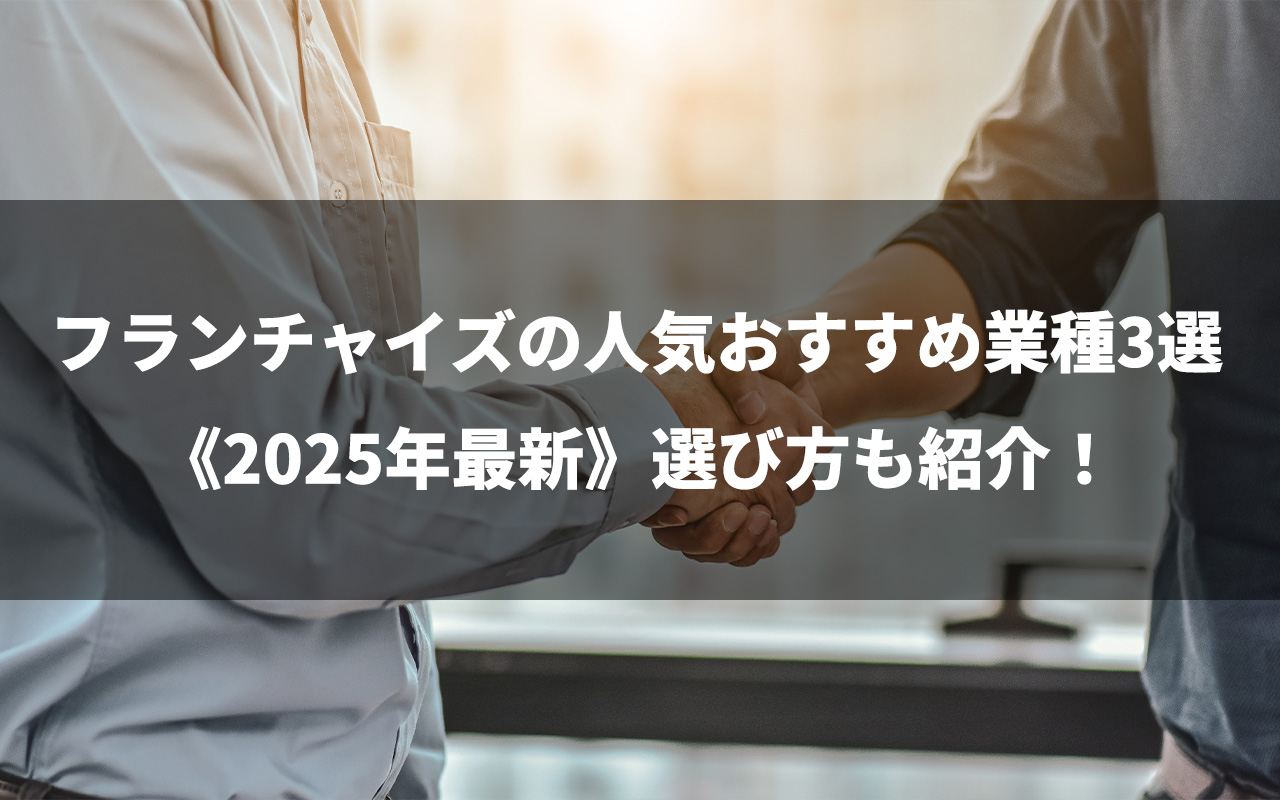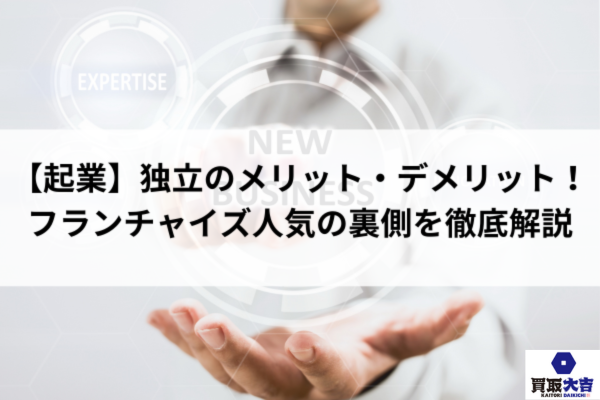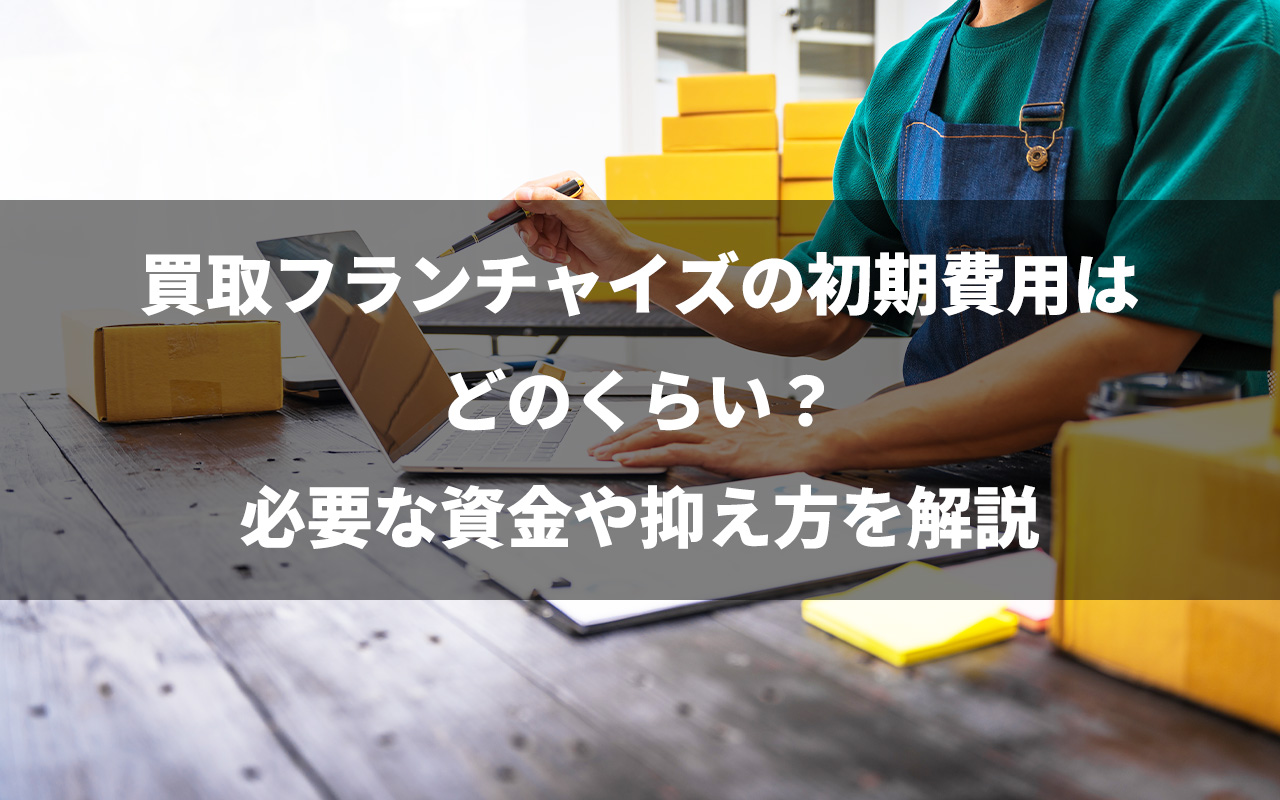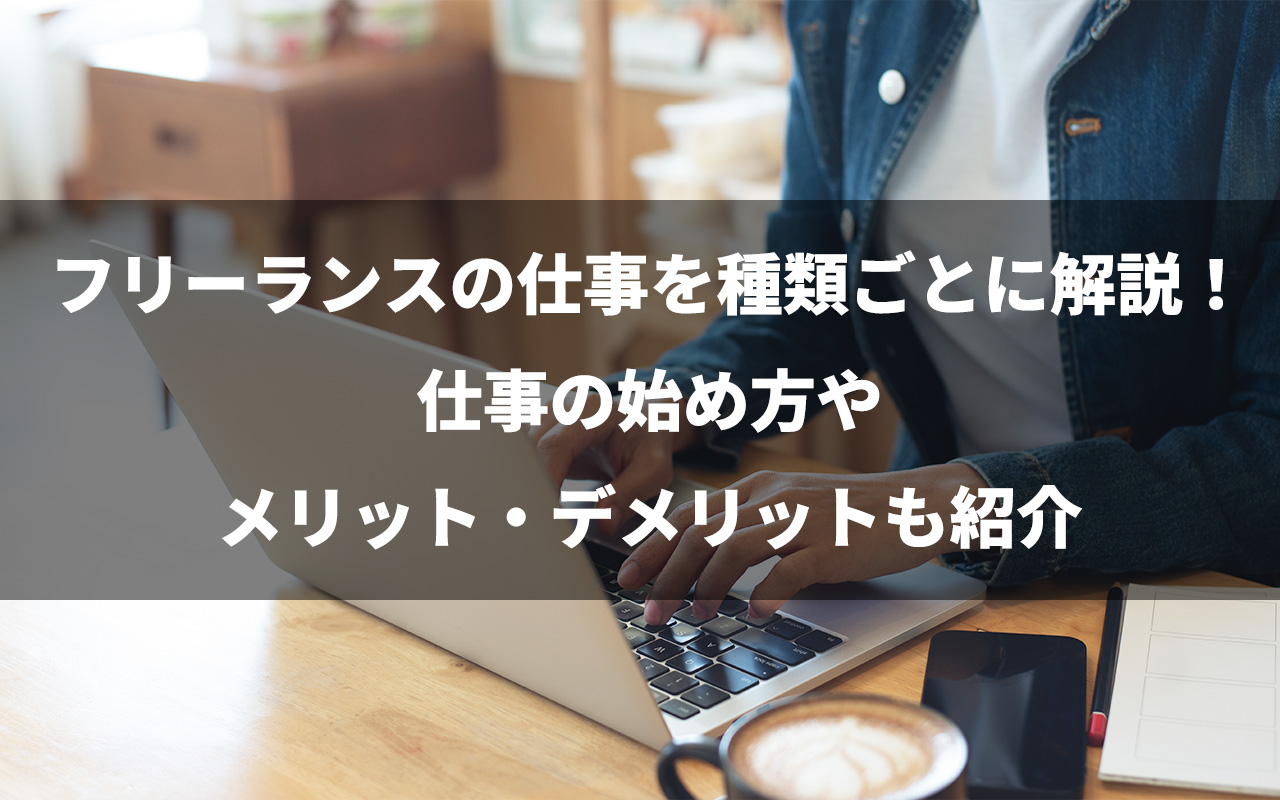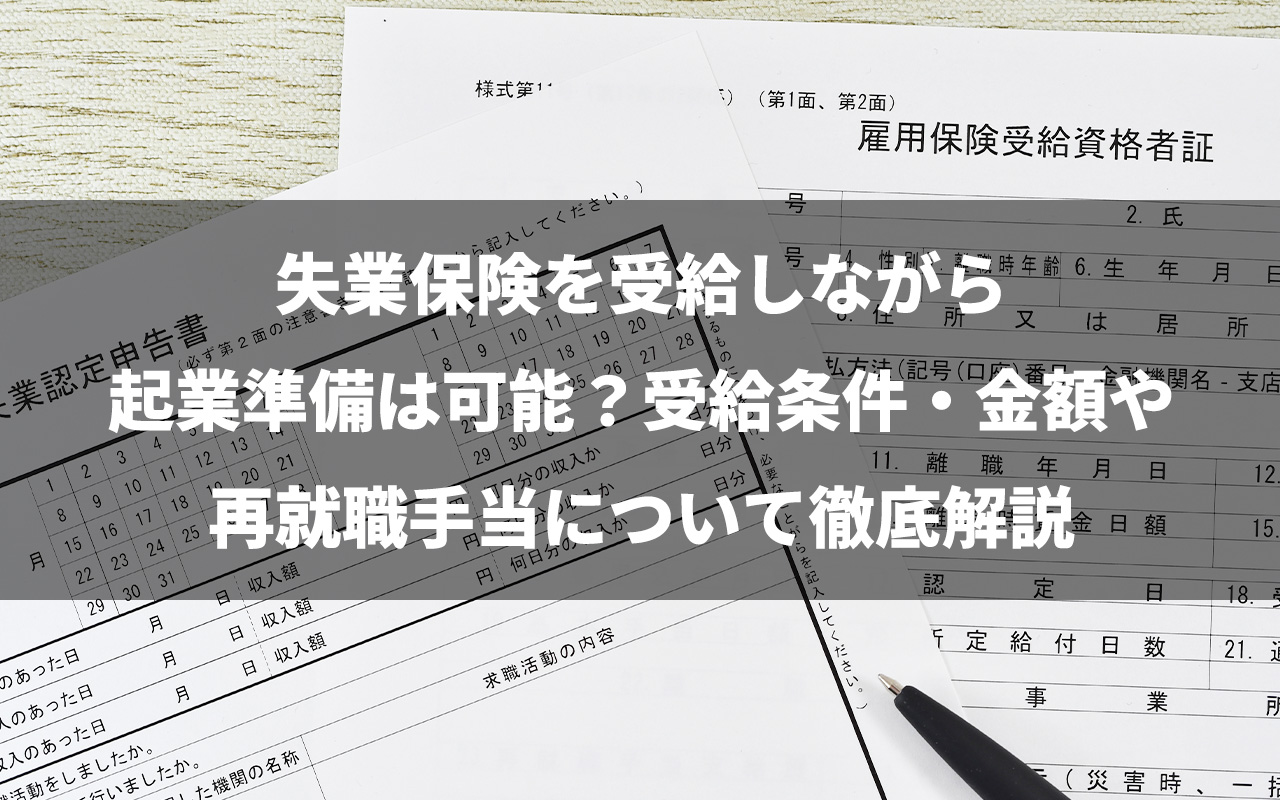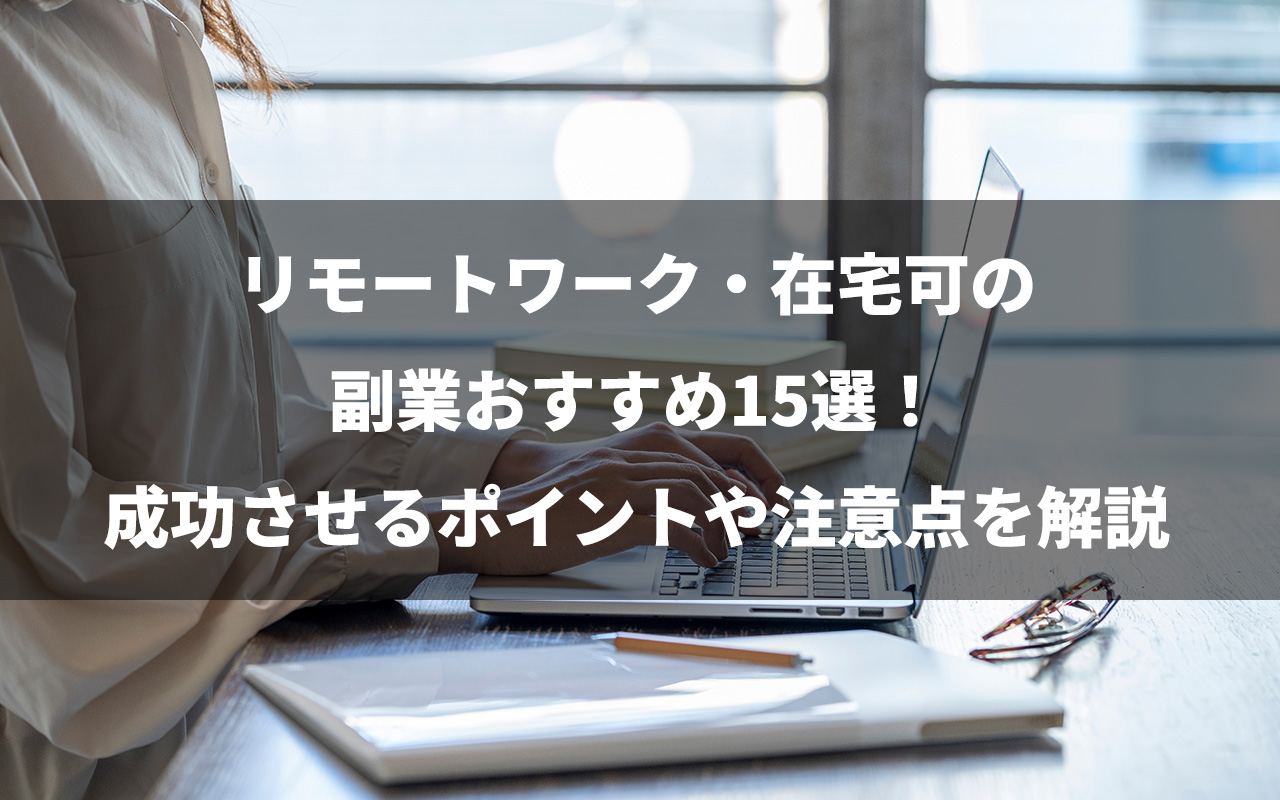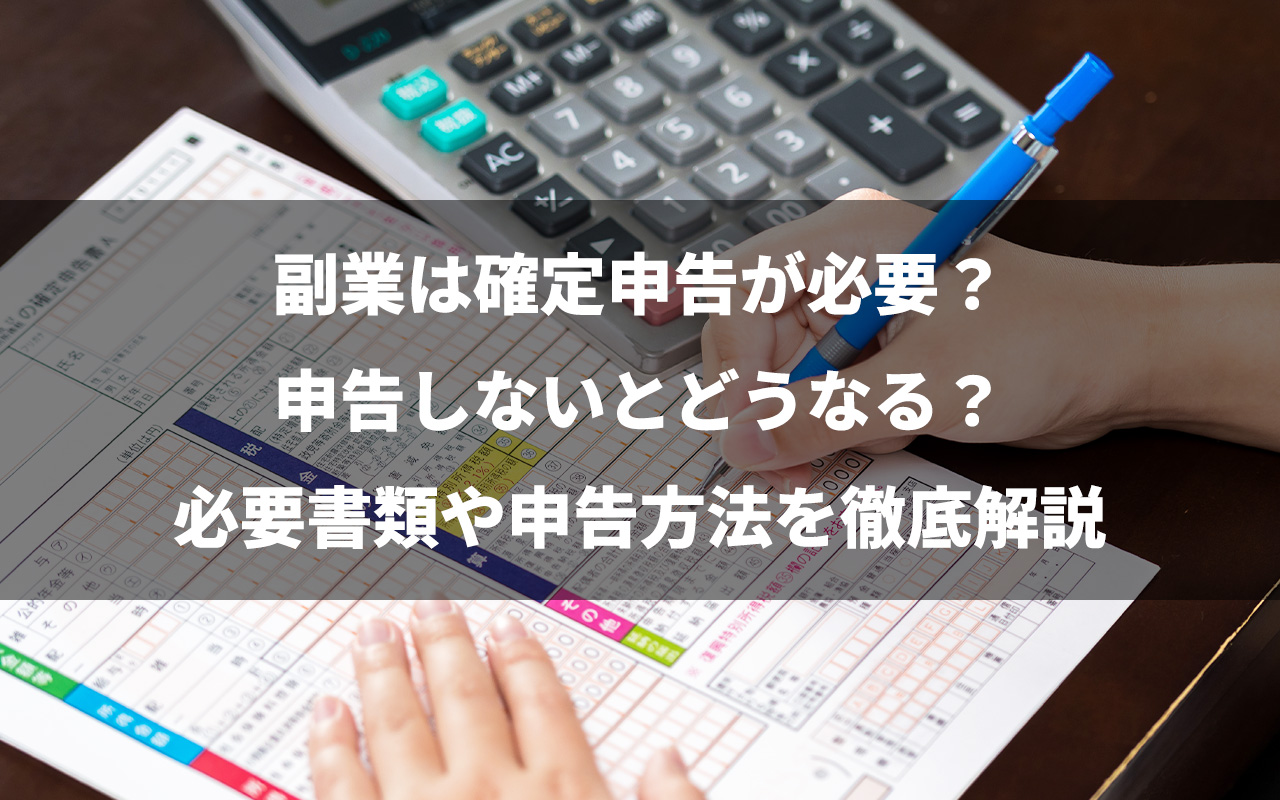近年、配送業の需要増加に伴い、個人運送業での開業に興味を持つ人も増えています。
大がかりな設備投資が必要ないことから比較的開業しやすく、労働の成果に応じて収入を増やせるという特長があります。
複数のメリットがある一方で、未経験での開業はハードルが高いと感じる方もいるでしょう。
そこで、この記事では個人運送業の開業方法や年収、稼げる秘密について詳しく解説します。個人運送業に興味がある人は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
個人運送業とは?

個人運送業とは、運送会社で正社員として働くのではなく、個人事業主として運送業を行うことです。柔軟な働き方ができることや、開業コストが比較的低いことから注目されている事業です。
ここからは、個人運送業の中でも軽貨物ドライバーに焦点を当てて、仕事内容や働き方について、詳しく解説します。
個人運送業(軽貨物ドライバー)の仕事内容
軽貨物ドライバーは大型トラックなどを使用せず、軽自動車やバイクなどを利用し、個人宅や企業が指定する場所へ荷物を配送する仕事です。
また、個人宅への配送は、インターネット通販の商品が中心ですが、不在時の再配送が発生しやすく、繁忙期は拘束時間が長くなる傾向があります。
一方、企業への配送では医薬品や精密機器、日用品などを扱い、定期的な契約を結べると安定した収益が見込めます。
荷物の丁寧な取扱いはもちろんのこと、時間管理能力や顧客対応力も求められる仕事と言えるでしょう。
個人運送業(軽貨物ドライバー)の働き方
軽貨物ドライバーの働き方は、比較的自由度が高いことが特徴です。自分のペースで仕事量を調整しやすく、労働時間や休日を自由に設定可能です。
基本的に指定されたエリアで配送するため、練度が高くなれば仕事の効率も上がり、収入の向上が見込めます。
成果をあげるためには、体力と自己管理能力はもちろん、自分の担当するエリアの地理や情報を把握した上で仕事を進めることが重要です。
個人運送業の種類

個人運送業は、大きく分けて以下の3種類です。
・業務委託のドライバー
・フリーランスのドライバー
・フランチャイズのドライバー
ここでは、上記3つについて解説します。
業務委託のドライバー
業務委託のドライバーは、運送会社と業務委託契約を結び、一部、あるいは全ての業務を依頼される形で仕事を請け負います。
業務委託には、成果に応じて報酬が発生する「請負契約」と、業務遂行自体に報酬が発生する「委任契約(準委任契約)」があります。
勤務時間や休日を自分で調整できますが、収入や成果は自己責任となる働き方です。
また、近年では守秘義務を守らず、業務請負した仕事内容等をインターネットで公開する行為が問題となっています。
契約は必ず遵守し、業務を遂行しましょう。
フリーランスのドライバー
フリーランスのドライバーとは、個人で直接契約し、仕事を請け負うドライバーのことです。運送会社と雇用契約を結ばないため、自分で営業して仕事を獲得する必要があります。
収入は完全な成果報酬型で、自分の裁量で仕事を選んだり、配送スケジュールを組み立てたりして、さまざまな案件に関わることも可能です。
しかし、社会保険や福利厚生、車両維持費は自己負担です。安定収入維持のため、常に仕事の確保を意識する必要があります。
フランチャイズのドライバー
フランチャイズのドライバーは、本部と呼ばれる運送会社のブランドや経営ノウハウを利用する代わりに、ロイヤリティと呼ばれる対価を支払います。一例として、ヤマト運輸でもフランチャイズ加盟者を募集しています。
前述した業務委託のドライバーと似ていますが、異なる働き方です。
具体的には、フランチャイズのドライバーは、本部が定めるルールに従わなければならず、自分のペースで仕事を進められる業務委託と比べて経営の自由度は低くなります。
しかし、本部のサポートや研修制度が充実しているため、未経験者でも安心して始められることがメリットです。
個人の軽貨物運送業が儲かるといわれている理由
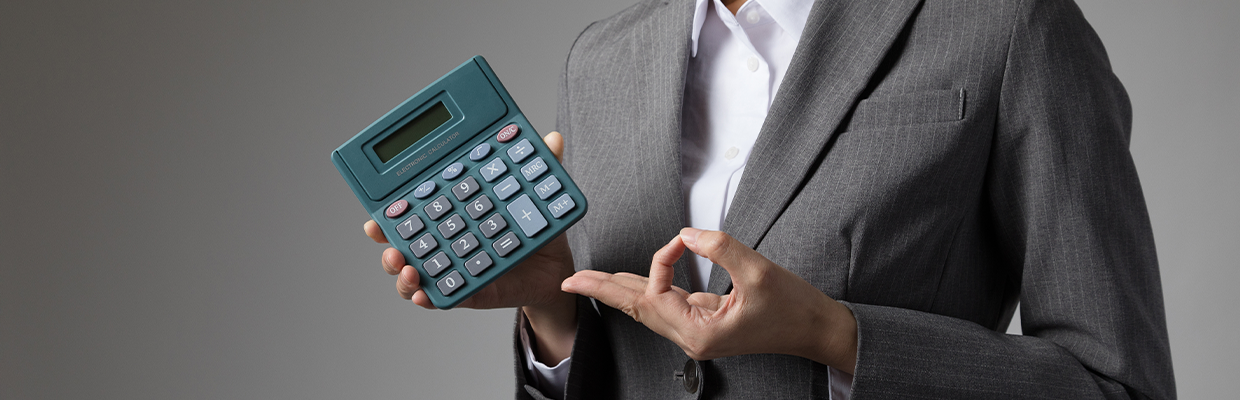
軽貨物ドライバーは、以下3つの理由から儲かるといわれています。
・働けば働くほど収入が得られる
・コロナ禍の影響で配送需要が伸びている
・経験を積めば効率が上がる
これらの理由について、順番に解説します。
働けば働くほど収入が得られる
軽貨物ドライバーのほとんどが、成果に応じて報酬を得られる歩合制です。そのため、業務を達成するほど収入を上げることができます。
特に繁忙期では、稼働時間を増やし、積極的に配送を遂行することで高収入を目指せます。
ただし、ドライバーは肉体労働であるため、体調不良には注意して業務に臨みましょう。
コロナ禍の影響で配送需要が伸びている
コロナ禍による配送需要の高まりも、軽貨物ドライバーに追い風となっています。宅配やデリバリーサービスが拡大し、コロナ禍の後も一般的となりました。
オンラインショッピングも以前より拡大し、商品の配送量が増加しています。また、配送業者は人手不足であるため、軽貨物ドライバーの需要が高まり、稼ぎやすい状況となっています。
経験を積めば効率が上がる
軽貨物ドライバーは、業務を繰り返すと、配送ルートやノウハウが身につき、効率的に業務を遂行できます。
その結果、配送量の増加に応じて収入も上昇します。
個人運送業は、経験が長いほど稼ぎやすくなる仕事と言えるでしょう。
個人の軽貨物運送業をやってはいけない・儲からないといわれている理由

個人の軽貨物運送業は稼げると考えられている一方で、やってはいけない・儲からないという意見もあります。主な理由は、以下の2つです。
・簡単に稼げるというイメージとギャップがある
・経費がかかる
それぞれどのような根拠があるのか、詳しく解説します。
簡単に稼げるというイメージとギャップがある
個人運送業は簡単に稼げると思われている傾向があります。これは、配送業界の広告によって、運送業は簡単に稼げるというイメージが定着しているためです。
しかし、前述のとおり、稼ぎやすい側面はあるものの、長時間労働になったり心身の負担が増したりすることがあるため、決して手軽な仕事ではありません。
このように、現実とイメージのギャップによって、儲からないと感じる方が多いのだと考えられます。
経費がかかる
経費がかかることも、個人運送業が稼げないといわれている理由の1つです。
貨物ドライバーのような運送業は、自動車を使用するため「燃料費」、「維持費」、「保険料」、「リース料(※)」などの経費が発生し、大きな負担となります。
仮に月収30万円を達成していたとしても、上記の経費が引かれるため、稼げないというイメージにつながるのでしょう。
※リース会社と呼ばれる企業が機械や設備を購入し、ユーザーがそれらを借り受ける際に支払う料金を指します。
個人の軽貨物運送業の開業方法

個人の軽貨物運送業は、以下の手順で開業できます。
(1)営業所を確保する
(2)軽貨物車両を準備する
(3)黒ナンバーを取得する
(4)任意保険に加入する
(5)個人事業主としての開業届を提出する
すぐに開業準備ができるように、それぞれの手順について理解を深めましょう。
(1)営業所を確保する
まずは、事業を営むための営業所を確保しましょう。これは、開業の際に運輸支局へ提出しなければならない書類に、営業所の情報を記入する必要があるためです。
また、軽貨物車を停車するための車庫も必要になります。原則として、車庫は営業所に併設している必要がありますが、併設できない場合は営業所から2km圏内であれば認められます。
さらに、乗務員が休憩・睡眠を行うための施設も用意しましょう。
これらの施設は、自己所有・賃貸のどちらでも問題ありませんが、土地の使用が確実であることが求められます。
(2)軽貨物車両を準備する
軽貨物車は中古車やカーリース(※)でも問題ありませんが、長距離運転の機会もあるため、可能な限り新しい軽貨物車がおすすめです。
また、二輪車を利用する場合は排気量が125ccを超える車種を選ぶ必要があります。
なお、軽貨物車を車検証に登録する際は、用途欄で事業目的である「貨物」を選択しましょう。
※リース会社と契約を結び、ユーザーが借り受ける自動車のことを意味します。
(3)黒ナンバーを取得する
軽貨物車を利用して運送業を開業するためには、必要書類を提出し、ナンバープレートを事業用の黒ナンバーに変更しなければなりません。
地域によって不要となる書類もありますが、黒ナンバーを取得するためには、運輸支局輸送担当に「貨物軽自動車運送事業経営届出書」、「事業用自動車等連絡書」、「運賃料金設定(変更)書」および「貨物軽自動車運送事業運賃料金表」、「車検証(完成検査証でも可)」を提出し、事業用自動車等連絡書の交付を受ける必要があります。
その後、運輸支局で交付された事業用自動車等連絡書を、敷地内にある軽自動車検査協会へ提出します。このとき、必要となる書類は事業主によって異なるため、手続きを始める前にホームページなどで確認しておきましょう。
黒ナンバーの登録が完了すると、事業用のナンバープレートを購入できるようになります。
出典:東京運輸支局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tokyo/kei_flow_001.html)
(4)任意保険に加入する
自動車やバイク(二輪自動車、原動機付自転車)を運行する際、法律によって自動車損害賠償責任保険(自賠責保険とも呼ばれます)への加入が義務付けられていますが、自賠責保険は人身事故の被害者救済を目的としているため、ドライバーの負傷や車・荷物等の破損は補償を受けられません。
そのため、任意保険への加入もおすすめします。ただし、一般的に任意保険の保険料は高額です。これは、事業用自動車は自家用車よりも走行距離や時間が長く、事故が発生する可能性が高いことに起因します。
また、依頼を受ける条件に任意保険の加入が含まれていることもあります。メリットがデメリットを上回る側面が多いため、強制保険だけでなく、任意保険も加入しておきましょう。
(5)個人事業主としての開業届を提出する
「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署へ提出すると、個人事業主としての事業活動が認められます。経費計上や青色申告も活用できるようになるため、確定申告における節税効果も期待できます。
開業届の提出期限は、事業開始等の事実があった日から1か月以内と定められています。軽貨物運送業の正式な開始と節税のため、開業届は提出しましょう。
軽貨物輸送の個人事業主に適用される補助金

補助金には返済義務がないため、開業資金の負担を大幅に削減できます。軽貨物輸送の個人事業主が活用できる補助金は、以下の2つが挙げられます。
・小規模事業者持続化補助金
・IT導入補助金
これらの補助金について、それぞれ詳しく解説します。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や生産性向上など、経営改善に向けた取り組みを支援する国家からの補助金です。
補助金は、大きく通常枠と特別枠の2種類に分類されます。一定の割合の範囲内であれば、通常枠では最大50万円、特別枠では最大200万円まで補助金を受け取ることができます。
参考:東京商工会議所
IT導入補助金
IT導入補助金は、規程で定められた中小企業や小規模事業者などを対象に、業務効率化や業務改善を目的としたITツールの導入を支援する補助金です。
また、補助額・補助率は申請枠やITツールの要件によって異なります。例えば、顧客対応・販売支援を目的としたITツールを導入する場合、通常は経費の半分以内の補助金を受け取ることができます。ただし、金額は5万円以上150万円未満に限られます。
参考:サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト
個人運送業を開業したときの年収

個人運送業の平均年収は350~400万円とされていますが、あくまで目安であるため労働時間や単価などによって変動します。
そこで個人運送業の年収について、以下の条件でシミュレーションしてみましょう。
・出勤日数:23日
・単価:150円
・1日の配送:120件
・手数料:10%
・ガソリン代:34,000円
・保険料:10,000円
・駐車場代:20,000円
1か月の売上は単価×配送料×出勤日数で求められます。この計算式に上記の条件を当てはめると、150×120×23=414,000となります。
しかし、この金額は売上であって月収ではありません。月収を導くためには、ここからさらに手数料や経費(駐車場代など)を差し引く必要があります。
これらの経費を差し引くと、月収は約30万円になるため、年収は約370万円であることがわかります。
個人運送業の経費内訳

ガソリン代
ガソリン代は走行距離(km)÷自動車の燃費(km/L)×ガソリン価格(円)で導くことができます。仮に150kmの距離を燃費15kmの軽貨物車で走行するとき、ガソリン価格が180円に設定されていた場合は、ガソリン代が1,800円であることがわかります。
また、近年のガソリンは価格が高騰しているため、燃費の良い車を選ぶことをおすすめします。
車の保険代
自動車の保険は、自賠責保険や運送業者貨物賠償保険(⾞両特定⽅式)などが挙げられます。
これらの保険料は、契約時に保険期間全体の保険料を一括で支払う一時払いが一般的です。
しかし、任意保険と同時加入等の条件を満たせば、クレジットカードを用いた分割払いに対応している保険会社もあります。
駐車場代
賃貸物件に駐車場が備わっている場合、駐車場代も賃料に合算して支払われます。また、自宅の駐車場を使用することで、コストを抑えることもできます。
なお、駐車場代は地域によって変動します。都心部に近づくほど高価になり、遠ざかるほど安価になる傾向があります。
メンテナンス代
軽貨物車のメンテナンス代には、以下の費用が含まれます。
・オイル交換
・バッテリー交換
・タイヤ交換
・洗車
・修理
特に、オイルやバッテリー、タイヤなどの消耗品の交換は定期的に行う必要があります。これらのメンテナンスを怠ると故障につながり、高額な修理費が発生するリスクが高まるため注意しましょう。
車検代
軽貨物車は、自家用車と同じく2年ごと(新車購入時のみ3年後)に車検を受ける必要があります。
また、車検の際に必要となる費用は、車種や自動車の状態、車検を受ける業者によってさまざまです。
サービスの内容が異なる場合もあるため、しっかりと事前調査をしておくとよいでしょう。
税金
軽貨物車に課せられる税金は「自動車税環境性能割(環境性能割)」、「軽自動車税(軽自動車税種別割)」、「自動車重量税」の3つです。
環境性能割は、自動車の燃費性能などに応じて、自動車を新規登録・移転登録等を行う際に納める税金です。
次に、軽自動車税は車検証に登録された所有者が毎年4月1日に納税する地方税です。税額は車種によって異なり、営業に使用する軽貨物車は3,800円と定められています。
最後に、自動車重量税は自動車の重量などに応じて課税される国税です。車検などの際に、その金額に相当する印紙を納付所に貼り付けて納付します。
出典:総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_12.html)
出典:総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_13.html)
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm)
運送業者に支払う手数料
個人運送業は、契約している元受けの運送会社に手数料を支払います。金額は企業によって異なりますが、一般的に売上の10~20%といわれています。
また、売上にかかわらず、毎月一定額の手数料が発生する定額制もあります。こちらは、フリーランスなどよりもフランチャイズ契約で多く見られる契約方式です。
経費で落とせない出費
経費として落とせない出費として、以下が挙げられます。
・借入れの元本
・業務外の自動車関連の費用
・所得税や住民税などの税金
・社会保険や生命保険などの保険料
・法律違反による違反金や反則金
経費は「事業の運営に関係する費用であるか否か」で判断されます。これらの出費を経費として計上すると、追加で税金が課せられるため注意しましょう。
個人運送業で開業するメリット

個人運送業のメリットは事業を始めるハードルが低いことです。軽自動車があれば、比較的容易にスタートできます。
また、自分で労働時間や休日を設定できるため、理想のライフ・ワーク・バランスを実現できるでしょう。さらに、労働が直接収入に反映されることで、モチベーションの維持にもつながります。
このような自由度の高さが、個人運送業ならではの大きなメリットと言えるでしょう。
個人運送業で開業するデメリット

個人運送業には、デメリットも存在します。
まず、経営者に該当するため、保険料や税金などの負担が大きい点です。
また、正社員と比較すると社会的信用が低いことも挙げられます。これにより、不動産契約やクレジットカードの審査が難しくなるおそれがあります。
さらに、経費や所得税の申告等の、あらゆる事務手続きを自らの手で行わなければなりません。
個人事業主は自営業者と同じように扱われます。上記のようなデメリットがあることも考慮しておきましょう。
買取ビジネスのフランチャイズで簡単に開業して稼ごう!

これまで、個人運送業の仕事内容やメリット・デメリットを解説しました。しかし、中には難しそうだと感じた方もいるかもしれません。
もしも、需要が高まっているビジネスに参入したいのであれば、買取ビジネスのフランチャイズで開業する方法もあります。
買取フランチャイズは多くありますが、特に「買取大吉」がおすすめです。「買取大吉」では、現在フランチャイズ加盟店を募集しています。
・店舗継続率96.4%(※)を可能にした「店舗OJTサポート」
・直営店の成功事例に基づいた「運営サポート」
・折り込みチラシやWeb広告を活用した「集客サポート」
・開業資金を調達する「創業融資サポート」
このように、開業前後の徹底したサポート体制が整っているため、未経験の方でも安心してスタートできます。
※2023年10月~2024年9月のデータです。
まとめ
今回は個人運送業の開業方法と稼げる理由について解説しました。
個人運送業は、近年の配達需要の急増によって案件が豊富であるため、成果に応じて収益を上げることができます。軽自動車があれば始められるため、新規でも参入しやすい業界と言えるでしょう。
また、フランチャイズ契約を結び、本部のサポートを受けながら働く選択肢もあります。この記事を参考に、自分だけの働き方について検討してみてください。